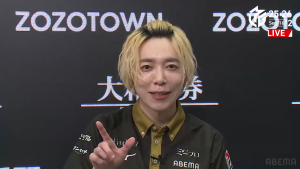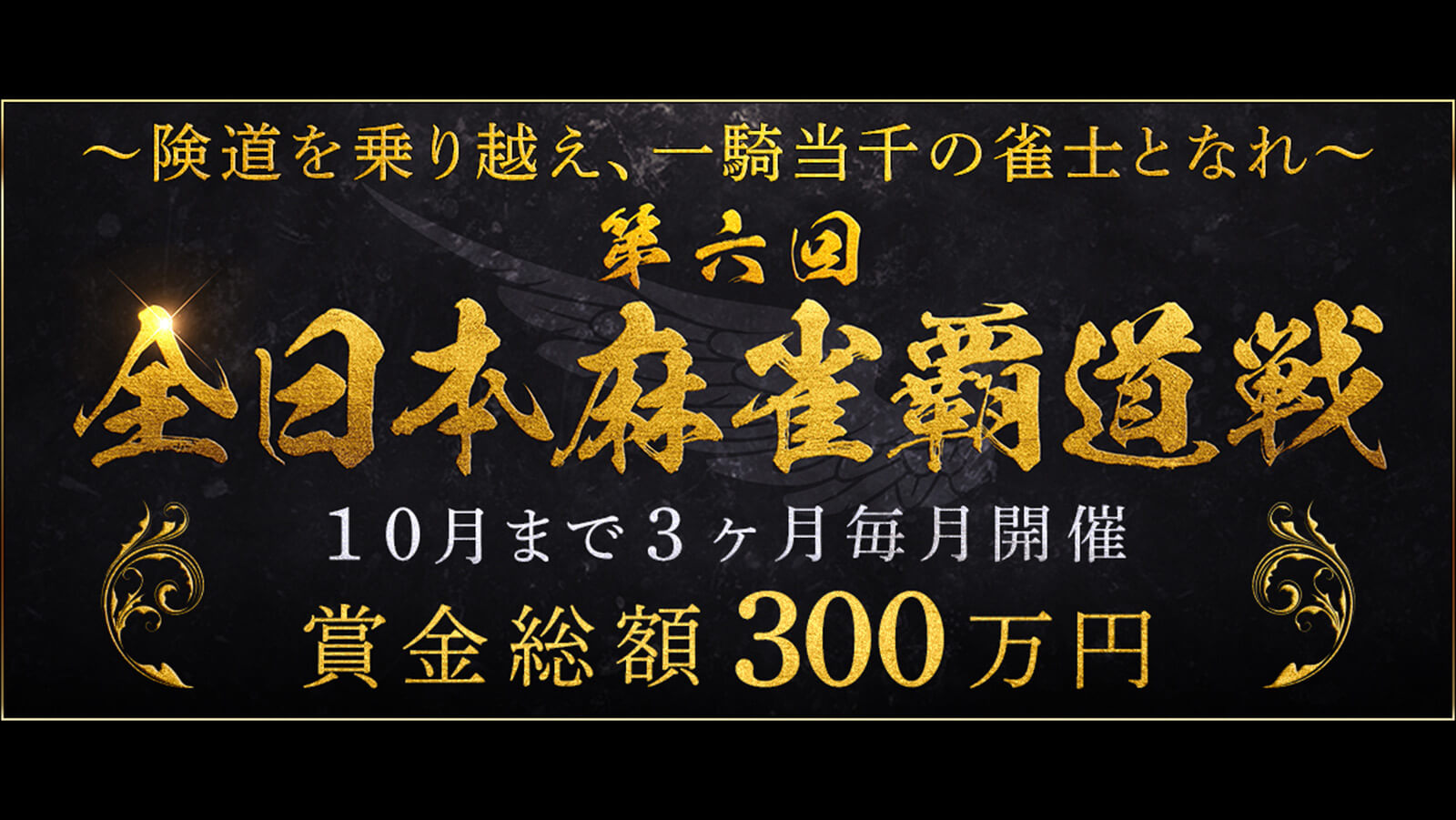回し打ちについて
これまで、押し引き判断は、テンパイなら押し、ノーテンなら降りが基本としてきましたが、押し引き判断表は、降りを選択した場合はその後は一切アガリ、テンパイを考慮ぜずにベタオリすることを前提としています。
よって、ベタオリと比較して押すかどうか微妙な手の場合は、アガリ、テンパイの可能性を残せる分、安全牌を切りつつ回し打ちする方が有力であるといえます。
「科学する麻雀」では、回し打ちは有効でないと書かれていましたが、これは
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() (
(![]() は片スジ、
は片スジ、![]() はスジ)
はスジ)
から打![]() という、安全とは言えない牌を切ったうえで、手牌の価値を大きく下げてしまうような「回し打ち」が損であるという意味であり、安全牌を切りつつアガリ、テンパイの可能性を残す例も含めた広い意味での回し打ちであれば、実戦で用いることは度々あります。
という、安全とは言えない牌を切ったうえで、手牌の価値を大きく下げてしまうような「回し打ち」が損であるという意味であり、安全牌を切りつつアガリ、テンパイの可能性を残す例も含めた広い意味での回し打ちであれば、実戦で用いることは度々あります。
もちろん、明確に押すべき手で押し、降りるべき手で降りるという基本的な押し引き判断、降りるなら正確に降りるというベタオリの精度を高めることの方が重要ではありますが、ベタオリの基礎を押さえたうえでは、「押すかどうか→(押すのがベタオリと比較して微妙または損なら)回し打ちの余地があるかどうか→あるなら回し打ち、ない、もしくは不要であるなら将来の他家のテンパイにも備えつつベタ降り」というように、ベタオリする前に回し打ちする手順がないかを考えることをお勧めします。
回し打ちの手順については、本で示した通りです。受け入れ枚数では基本的に、くっつき1シャンテン>ヘッドレス1シャンテン>2面子1シャンテンであるという手作りの項目で取り上げた手牌に関する知識を押さえておけば、何を切って回し打ちするのがよいかも判断しやすいと思います。具体的にはこちらも参考にしたいただければ幸いです。
この連載の目次ページを見る