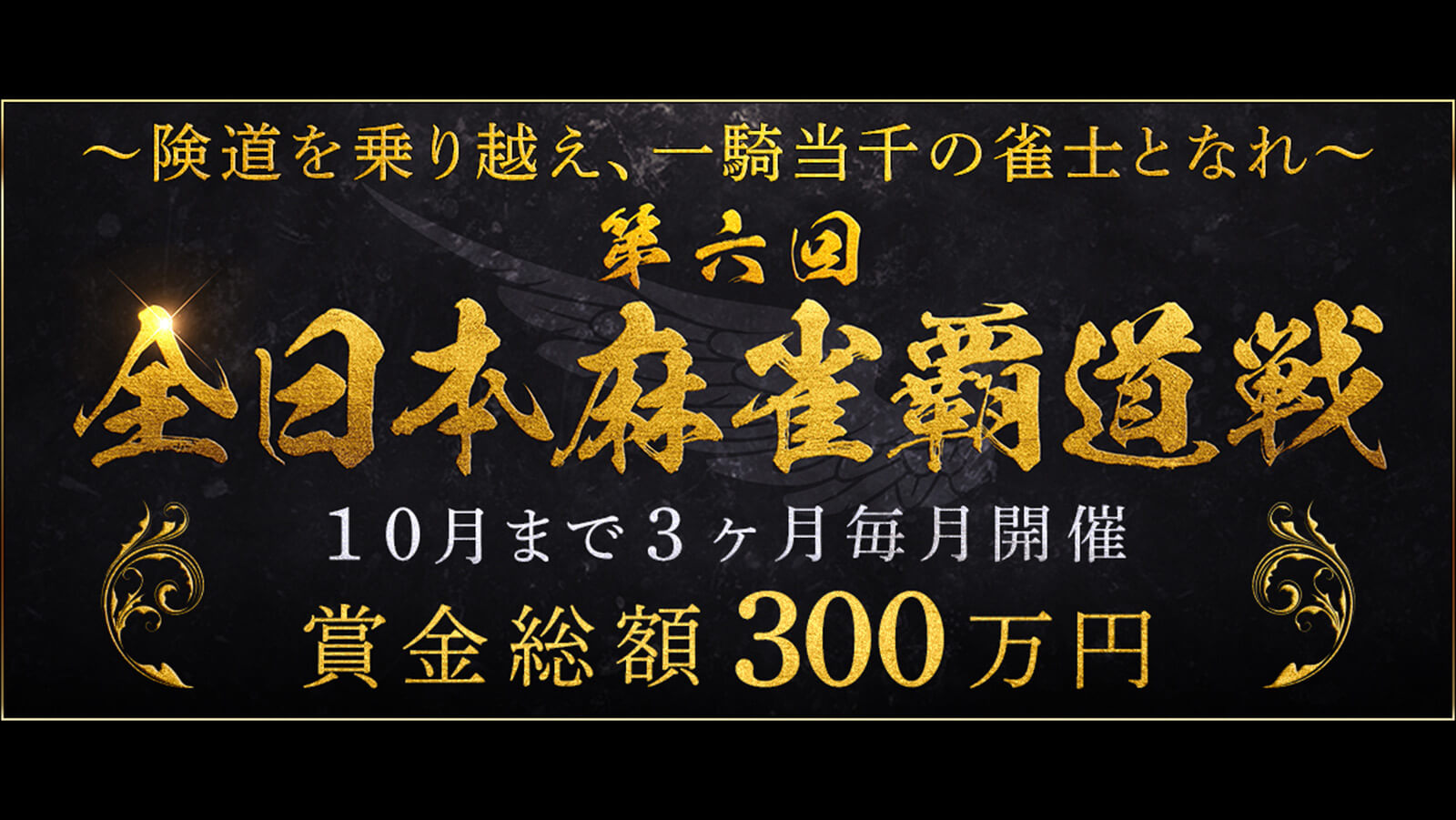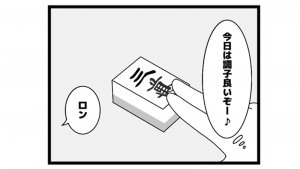配牌A ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
配牌B ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ドラは![]() として、配牌Aは
として、配牌Aは![]()
![]()
![]() の3メンチャンテンパイ。しかも
の3メンチャンテンパイ。しかも![]()
![]() なら高め三色までつくタンピンドラドラの手。一方配牌Bはメンツだけでなく雀頭もターツもドラも無し。メンツ手8シャンテン。チートイツ6シャンテン、国士無双7シャンテン。Aは最高に近い配牌で、Bは限りなく最低に近い配牌。条件無しなら誰しもがAの方がよいと言うでしょう。
なら高め三色までつくタンピンドラドラの手。一方配牌Bはメンツだけでなく雀頭もターツもドラも無し。メンツ手8シャンテン。チートイツ6シャンテン、国士無双7シャンテン。Aは最高に近い配牌で、Bは限りなく最低に近い配牌。条件無しなら誰しもがAの方がよいと言うでしょう。
しかしこれが優勝のみ評価される大会オーラス。圧倒的なダントツの親で後は局が流れるだけで優勝となれば価値に大差ありません。むしろBだった場合、ベタオリするだけでよい時にこの配牌が来てよかったと安堵するかもしれません。
更に言えば、親がダントツで、逆転には役満が必要な子の立場であれば、配牌Aが来てもただがっかりするだけです。配牌Bの方がまだ国士無双か四喜和で希望が残ります。
今回は喩えが極端でしたが、手牌の良し悪しというのはあくまで主観的な評価で、条件次第で変化する可能性があるものです。一方、何シャンテンの手か、待ちは何か、アガった時にどんな役がつくかというのは、ルールが決まっていれば条件次第で変化することがない客観的な評価と言えます。
人が書いて人に読ませる必要がある以上、戦術書も主観的な評価が多々入ります。私自身、好配牌、悪配牌と表現してしまうことが多いですが、麻雀で勝つために判断の精度を高めるうえでは、手牌や局面をなるべく、「ありのまま」の形で評価できる方が望ましいと言えましょう。
さて、勝つためにと書きましたが、これが勝ち負けは二の次で、楽しむことが第一だとしても、「ありのまま」の形で評価できる方が望ましいのではないでしょうか。麻雀はただでさえ、自分の思い通りにはならないゲーム。アガリやすく高打点が容易に狙える手が毎回くれば楽しいものですが、実際は配牌Bほどではなくても、アガリが遠く、アガれたところで高打点にはなりづらい手が来ることが多いものです。
そのような手を全て「悪配牌」で片付けてしまえば、勝つだけではなく、楽しむことも難しいものです。アガリが遠いなりに、アガリを目指す手順がある。アガリが無理だとしても、よりよい結果の為にできることがある。そのことに気付き実戦するためには、手牌や局面をできるだけありのままに評価できるようになる必要があります。
勝つ為の麻雀と楽しむ為の麻雀。両者は別物だから棲み分けが必要という意見をよく聞きます。確かにそれは事実ではあるのですが、それでも根っこのところは同じ麻雀です。細かな違いも区別できるようになることが賢明になるということではありますが、それぞれが違うけれど、それでも同じなのだという価値観を、今後も伝えていきたいと思うところであります。