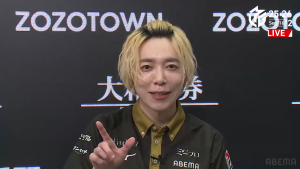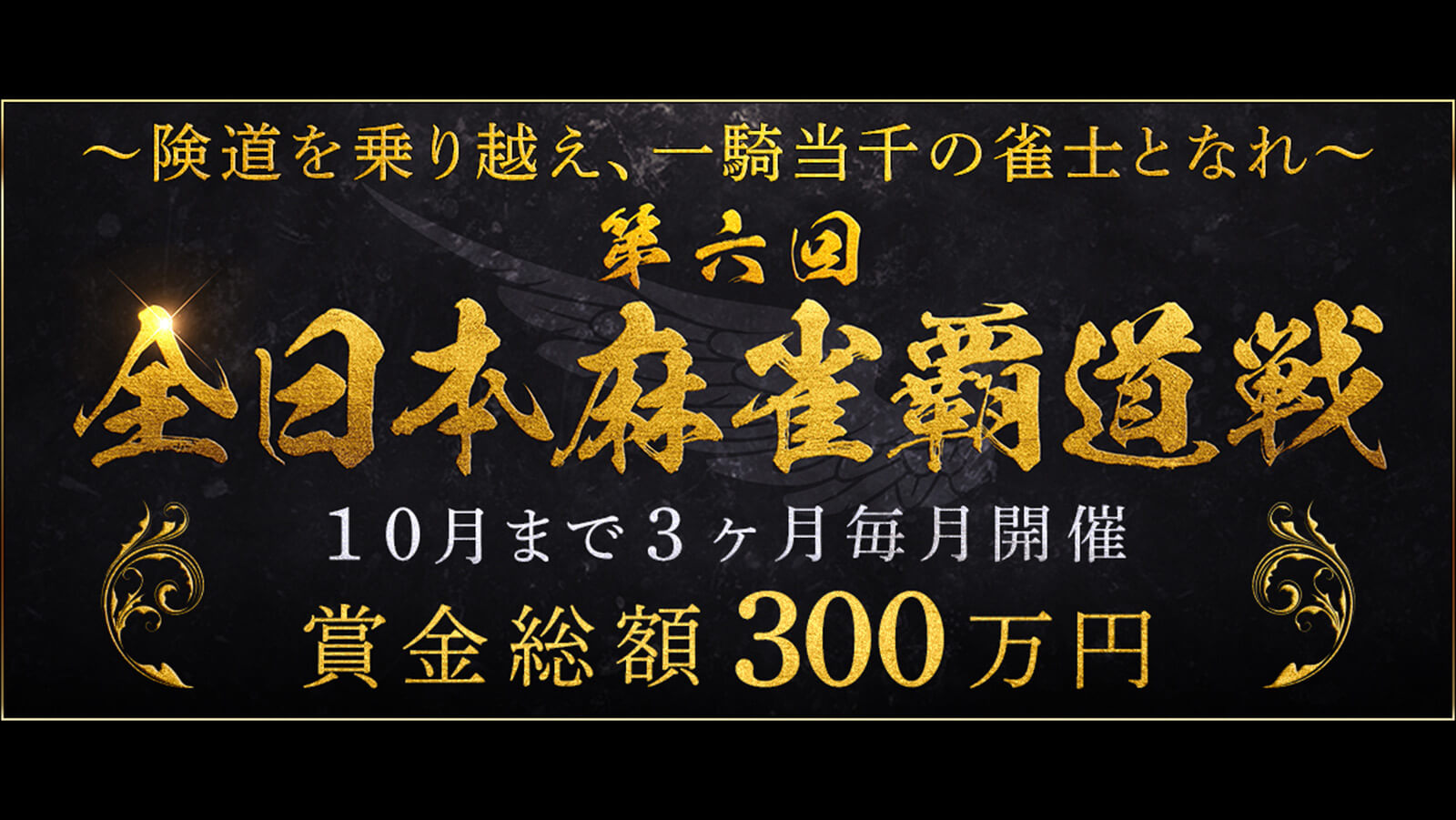![]()
![]()
![]()
![]() とあるところから
とあるところから![]() をチーして、
をチーして、![]()
![]() のリャンメンを残すような鳴きを「食い伸ばし」と言います。では、
のリャンメンを残すような鳴きを「食い伸ばし」と言います。では、![]()
![]()
![]()
![]()
![]() とあるところから
とあるところから![]() をチーして、
をチーして、![]()
![]() のカンチャンを
のカンチャンを![]()
![]() のリャンメンにするような鳴きを何と言うでしょうか。そうです。これも「食い伸ばし」と言います。
のリャンメンにするような鳴きを何と言うでしょうか。そうです。これも「食い伸ばし」と言います。
しかし、前者は浮き牌をターツにしているのに対して、後者はターツを別のターツに変化させているのですから、同じ「食い伸ばし」でも性質が異なります。
同じ言葉が別の意味を指すということは多々ありますが、違う性質のものに同じ言葉が使われるのは混乱のもとでもあります。例えば「ターツ落とし(が入っている)仕掛けに食い伸ばし無し(食い伸ばしの形では当たらない)」というセオリーがありますが、ここでの「食い伸ばし」は前者の意味であり、後者についてはその限りではありません。
食いのばしというのは正式なルール用語というわけでもありませんし、この用語を日常的に使用している時点で、前者と後者の区別がついている方がほとんどだとは思いますが、体系的な戦術書を記すうえでは気になるところでもあります。よって『勝つための現代麻雀技術論』では、前者を「食いちぎり」、後者を「食い伸ばし」と表現することにしました。
また、![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() とあるところから
とあるところから![]() をチーして、
をチーして、![]()
![]()
![]()
![]() の中ぶくれを残すような鳴きについても「食い伸ばし」と言われる場合がありますが、これもメンツから浮き牌を作るという別の性質を持つ鳴きなので、「食い残し」と表現することにしました。
の中ぶくれを残すような鳴きについても「食い伸ばし」と言われる場合がありますが、これもメンツから浮き牌を作るという別の性質を持つ鳴きなので、「食い残し」と表現することにしました。
とはいえ、それまで使われていなかった表現はなかなか浸透しないものです。一部に浸透したとしても、今度は本書を読んだことの無い方にとっては、ますます混乱させる要因になる恐れもあります。
それまで用いられてきた麻雀用語に沿って解説するのも、新しく用語を作るのも相応の問題が起こります。ここ数年はこの問題で悩むことが多かったのですが、今後は「ルール上どうしても必要な麻雀用語」以外は、用語を用いる代わりに見たままを簡潔に書くことを意識したいと思います(徹底できる自信はありませんがご了承下さい)。例えば「食い伸ばし」は、鳴く前のターツ→鳴いた後残るターツ、「食いちぎり」は、鳴く前の浮き牌→鳴いた後残るターツ、「食い残し」は、鳴く前のメンツ→鳴いた後残る浮き牌のように表します。
それはそれで従来の表現に慣れ親しんでいる人にとって違和感を覚えるものになりそうですが、麻雀における技術には、一定以上の実力が無ければ理解すら難しい類のものは滅多にないので、「定義が明瞭な言葉を用いる」「そのうえで専門用語は最低限に留める」ことによって、誰しもが、「見れば分かる」形の戦術講座が望ましいと思ったことであります。