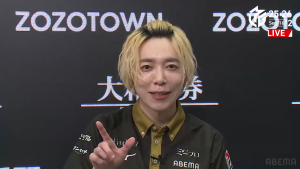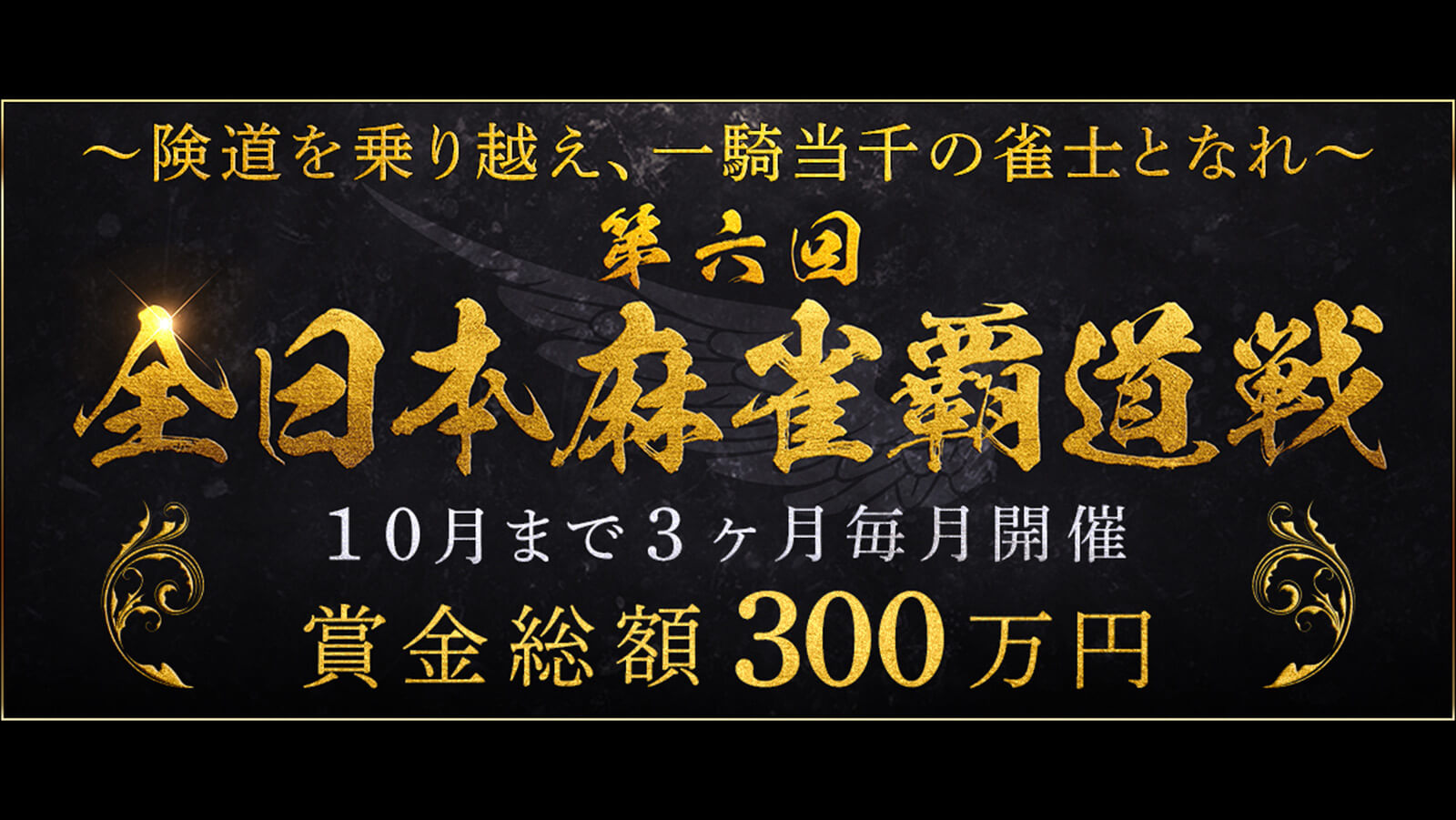システム4
子の1シャンテンから無スジ勝負(テンパイ時に切る牌も無スジ)となると、基本的に良形(リャンメン×2以上)かつ高打点(満貫程度)が必要になります。(2)の手牌は辛うじて基準を満たしているとも言えますが、本書で指摘されているように、ドラ表示牌![]() は浮き牌として強い部類なので、悪形低打点テンパイになりやすい手牌ならもっと引っ張られると予想されるので、通常より良形テンパイの可能性が高く、ドラ
は浮き牌として強い部類なので、悪形低打点テンパイになりやすい手牌ならもっと引っ張られると予想されるので、通常より良形テンパイの可能性が高く、ドラ![]() を持たれていることも多いとみて降りを選ぶことになりそうです。
を持たれていることも多いとみて降りを選ぶことになりそうです。
危険牌を2枚以上押すことが確定していることがオリ寄りの判断ポイントとありますが、危険牌を押すのが1枚以下で済むということは(テンパイ時に切る牌が1シャンテン時に通した牌と同じ牌やスジになるケースを除き)、1シャンテン時に切る牌は安全牌ということなのでそもそも押すかどうかあまり迷いません。押すかどうかが問題になる時点で危険牌を2枚以上押すことは大体確定しているので、やはり1シャンテンからは基本は降りることになると言えそうです。
システム5
通れば高確率で加点できることから、流局間際のケイテン押しは案外見合うことが多いものです。アガリを目指す選択に比べるとケイテン取りはどうしても軽視しがちなので、ケイテンを取る発想が希薄な方は今以上に意識を向けた方がいいと思います。
一方、昨今の戦術書でケイテンの重要性を意識できている方は、本項のまとめに書かれてあるような諸要素をふまえたうえで、通ればテンパイ料確定としても実戦では案外押さないこともあることに注意しましょう。基本的な基準を押さえていれば切る牌が比較的通しやすい牌や、テンパイ料の価値が高い局面であればあまり迷わずにテンパイに取れるものなので、迷った時点でオリ寄りの要素があるものです。残りツモがまだあるなら、危険牌を止めて次巡以降のツモでより安全にテンパイを取れる可能性も残るのでなおさらです。
ケイテン押し引きの基準からすると、32ページの3s![]() は残りツモ1回(残り2巡)でも通してよさそうですが、
は残りツモ1回(残り2巡)でも通してよさそうですが、![]()
![]() 待ちは
待ちは![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() あたりの無スジよりは可能性が高いので、残りスジ9本とはいえ実質6本くらいかもしれません。そうすると最後のツモで無スジを引いた場合に押すかどうか微妙になるので、この時点で
あたりの無スジよりは可能性が高いので、残りスジ9本とはいえ実質6本くらいかもしれません。そうすると最後のツモで無スジを引いた場合に押すかどうか微妙になるので、この時点で![]() は止めた方が無難かもしれませんね。ルールや点数状況的に放銃のリスクが大きいならなおさらです。
は止めた方が無難かもしれませんね。ルールや点数状況的に放銃のリスクが大きいならなおさらです。
オリ本 ~天鳳位が語る麻雀・守備の極意~
 本書は第9代天鳳位であるしゅかつ氏が「オリ」について語った一冊です。とはいえ「相手から攻め込まれた瞬間」にどうやってオリるかを解説したものではありません。その前の段階や後の段階の技術(=大局観)を総合的に説明することで、押し引きを点ではなく線で捉えられるようになっています。それと同時に、「こんなケースでは思考停止でベタオリで良い」といった考えなくて良いケース、というのも説明しています(=システム化)。これらの大局観とシステム化の両輪によって本書はより汎用的なオリの技法を説いたものとなり、これまでの麻雀の守備戦術本とは一線を画す、ハイレベルな内容になっています。本書で現代麻雀の最高レベルの「可能な限り失点を防ぐ技術」を体得してください。
本書は第9代天鳳位であるしゅかつ氏が「オリ」について語った一冊です。とはいえ「相手から攻め込まれた瞬間」にどうやってオリるかを解説したものではありません。その前の段階や後の段階の技術(=大局観)を総合的に説明することで、押し引きを点ではなく線で捉えられるようになっています。それと同時に、「こんなケースでは思考停止でベタオリで良い」といった考えなくて良いケース、というのも説明しています(=システム化)。これらの大局観とシステム化の両輪によって本書はより汎用的なオリの技法を説いたものとなり、これまでの麻雀の守備戦術本とは一線を画す、ハイレベルな内容になっています。本書で現代麻雀の最高レベルの「可能な限り失点を防ぐ技術」を体得してください。
Kindle:1,497円
購入はこちら