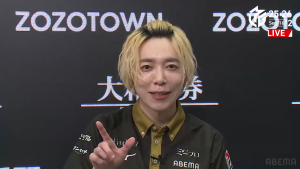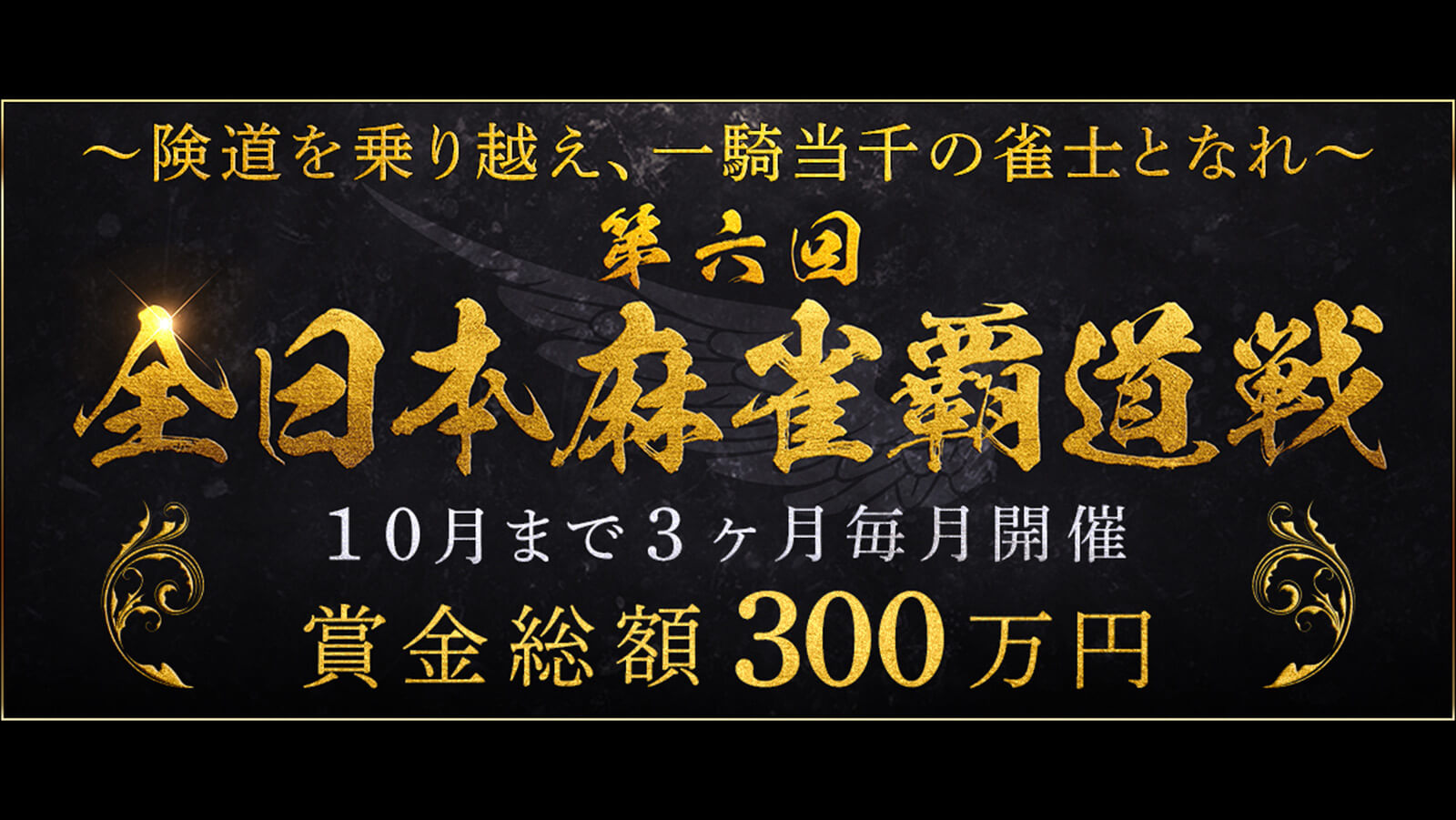- 『ネマタの戦術本レビュー』は、麻雀戦術サイト「現代麻雀技術論」の著者・ネマタさんによる戦術本レビューです。
- ご意見・ご感想がありましたら、お問い合わせフォームから送信してください。
- 第1回から読みたい方は、目次からご覧ください!
第1章 セオリー16
今回からは最後の手出し牌がターツと読めるケースの判断。141ページのような局面になった場合に、南家は東家の![]() を鳴いていないから通ると判断してしまう人もいるかもしれません。今回は東家の
を鳴いていないから通ると判断してしまう人もいるかもしれません。今回は東家の![]() より先に南家が
より先に南家が![]() を切っているので、まだ
を切っているので、まだ![]()
![]() のターツが無かったケースは考えにくいですが、メンツ候補が足りていない、あるいはダブドラ
のターツが無かったケースは考えにくいですが、メンツ候補が足りていない、あるいはダブドラ![]() が手の内に無かった等の理由で、手牌を短くしてまで
が手の内に無かった等の理由で、手牌を短くしてまで![]()
![]() からは鳴きたくなかったというケースは有り得ます。一方、
からは鳴きたくなかったというケースは有り得ます。一方、![]()
![]() 待ちでないのに、ここまで
待ちでないのに、ここまで![]() を引っ張った理由を想定するのは難しいですから、
を引っ張った理由を想定するのは難しいですから、![]()
![]() 待ちはやはり大本命とみるべきでしょう。 もし
待ちはやはり大本命とみるべきでしょう。 もし![]() と
と![]() の順が逆ならどうでしょう。これも
の順が逆ならどうでしょう。これも![]() が1枚切れなら
が1枚切れなら![]()
![]()
![]()
![]() 頭頭からの
頭頭からの![]() 切りはありますし、そうでなくても何となく
切りはありますし、そうでなくても何となく![]() から切る打ち手も居そうですが、今度はむしろ
から切る打ち手も居そうですが、今度はむしろ![]()
![]()
![]() や
や![]()
![]()
![]() からの打
からの打![]() で
で![]() と何かのシャンポンやカン
と何かのシャンポンやカン![]() が本線になります。このケースも、リャンメンを落としているからリャンメン以外の待ちには通ると思い込んでしまう人がいるかもしれません。セオリー3でも取り上げられましたが、元々待ちが絞りやすいケースで「通りやすそう」という読みを安易に用いるとミスをしがちです。
が本線になります。このケースも、リャンメンを落としているからリャンメン以外の待ちには通ると思い込んでしまう人がいるかもしれません。セオリー3でも取り上げられましたが、元々待ちが絞りやすいケースで「通りやすそう」という読みを安易に用いるとミスをしがちです。
今回のように待ちを読まれやすくなる受けについては先切りも候補に上がりますが、鳴き手はポンして手を進めることもできるのでメンゼン時より受け入れのロスも大きくなります。143、145ページのような手牌なら、1手進んだ時に安牌を抱えていた方がよいなら先切りするくらいがちょうどよさそうですが、もしマンズが![]()
![]()
![]() なら
なら![]() を切ってもロスは
を切ってもロスは![]() のみ。これならドラ
のみ。これならドラ![]() であっても
であっても![]() 先切りがよさそうです。
先切りがよさそうです。
現代麻雀の秘技 相手に対応させる技術

基礎的な麻雀戦術理論がネット上で共有されたことで、麻雀ファン全体のレベルが上がったと言われています。その中で差をつけるための技術として、今注目を集めているのが「相手に対応させる技術」です。相手の「対応する技術」を逆手に取って、その裏をかくハイレベルなテクニックとなります。
本書ではそのような戦術を論理的な解説に定評のある平澤元気プロが説明します。
(1)読みの基礎
(2)それを応用する技術
(3)ただしこれはやりすぎ
本書で基本的な読みのテクニックとその裏をかく技術をマスターしてください。
購入はこちら