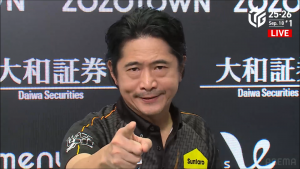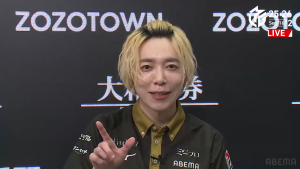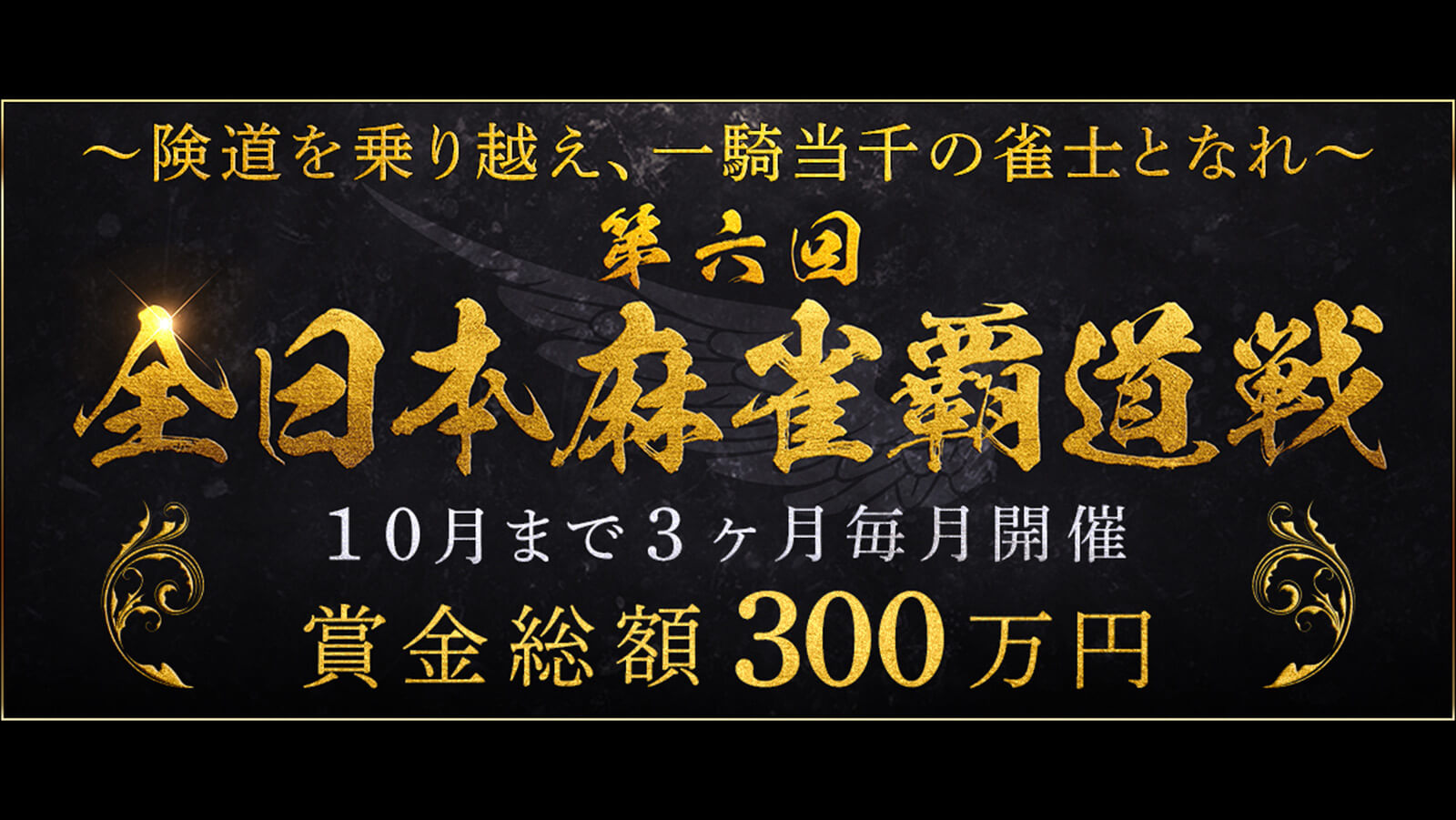ラス目の西家がドラ![]() をポン。高打点確定の仕掛けなのでマークが必要ですが、ドラ
をポン。高打点確定の仕掛けなのでマークが必要ですが、ドラ![]() トイツ以外は面子候補が揃っていない遠い仕掛けも否定できないので、まだテンパイしていない可能性が高そうです。
トイツ以外は面子候補が揃っていない遠い仕掛けも否定できないので、まだテンパイしていない可能性が高そうです。
こちらは面子候補オーバーの2シャンテン。形としては![]()
![]()
![]() のリャンメントイツを残して打
のリャンメントイツを残して打![]() (打
(打![]() との差はマンズ一通への変化)とするところですが、西家の仕掛けが更に入ってテンパイ率が高くなると、完全1シャンテンになっても押しづらい。
との差はマンズ一通への変化)とするところですが、西家の仕掛けが更に入ってテンパイ率が高くなると、完全1シャンテンになっても押しづらい。
一方リャンメン×2の1シャンテンでも、![]() か
か![]() トイツのうち、その時点で放銃しにくい方を切れば、次にテンパイした時は1巡前に通った牌を切れるので押しやすい。将来の放銃率も
トイツのうち、その時点で放銃しにくい方を切れば、次にテンパイした時は1巡前に通った牌を切れるので押しやすい。将来の放銃率も![]() よりは端牌の
よりは端牌の![]()
![]() の方が低いので
の方が低いので![]() を先に切ってみました。
を先に切ってみました。

![]() をチーして打
をチーして打![]() 。3フーロともなるとほぼテンパイですが、
。3フーロともなるとほぼテンパイですが、![]()
![]() とカンチャンを手出しで落としているので、
とカンチャンを手出しで落としているので、![]() が当たるとすれば
が当たるとすれば![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 頭頭からポンできる受けを消してまで
頭頭からポンできる受けを消してまで![]() を先に切ったことになります。既にドラをポンしているとなるとなおさら考えにくいです。
を先に切ったことになります。既にドラをポンしているとなるとなおさら考えにくいです。

それならこちらもアガリを目指すことに越したことは無いので打![]() 。逆に、
。逆に、![]() を面子候補の一部とする形。
を面子候補の一部とする形。![]()
![]()
![]() 頭頭から打
頭頭から打![]() で
で![]()
![]() 、
、![]()
![]()
![]() 頭頭から打
頭頭から打![]() でカン
でカン![]() は結構ありそう。結果論かもしれませんが
は結構ありそう。結果論かもしれませんが![]() 先切りが活きる展開となりました。
先切りが活きる展開となりました。

メンゼン相手にはどの辺りでテンパイするかも、どこが待ちになるかも読みにくいので、安牌を抱えることはあまり考えず先制テンパイを目指し、後手を引いたら降りるという打ち方が有力であることが多いです。
昨今の麻雀のルールはドラが多いので、メンゼンリーチなら手役関係無く高打点になりやすいので尚のことこの傾向が強いと言えます。
一方、テンパイが入るタイミングもテンパイ時の待ちもある程度読みを入れることが可能な鳴き手に対しては、テンパイ率が若干落ちる程度なら、将来放銃しやすい牌を先に切っておいて、後手を踏んだ場合も押し返せる手順が残るようにしておくことも有力になることもそれなりにあると考えます。
「これくらいからは先切り有利」という基準を作るのは困難なので、戦術本ではどうしても取り上げにくい内容ですが、常に将来の安牌よりテンパイする受け入れを優先すべきというわけではないというのも間違いありません。
「アガリに近い段階の受け入れ優先」を原則としては押さえつつも、実戦ではセオリーそのものにはあまり固執せずに打たれることをお勧めします。