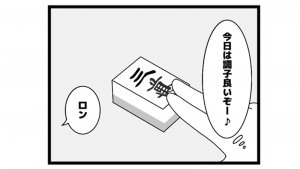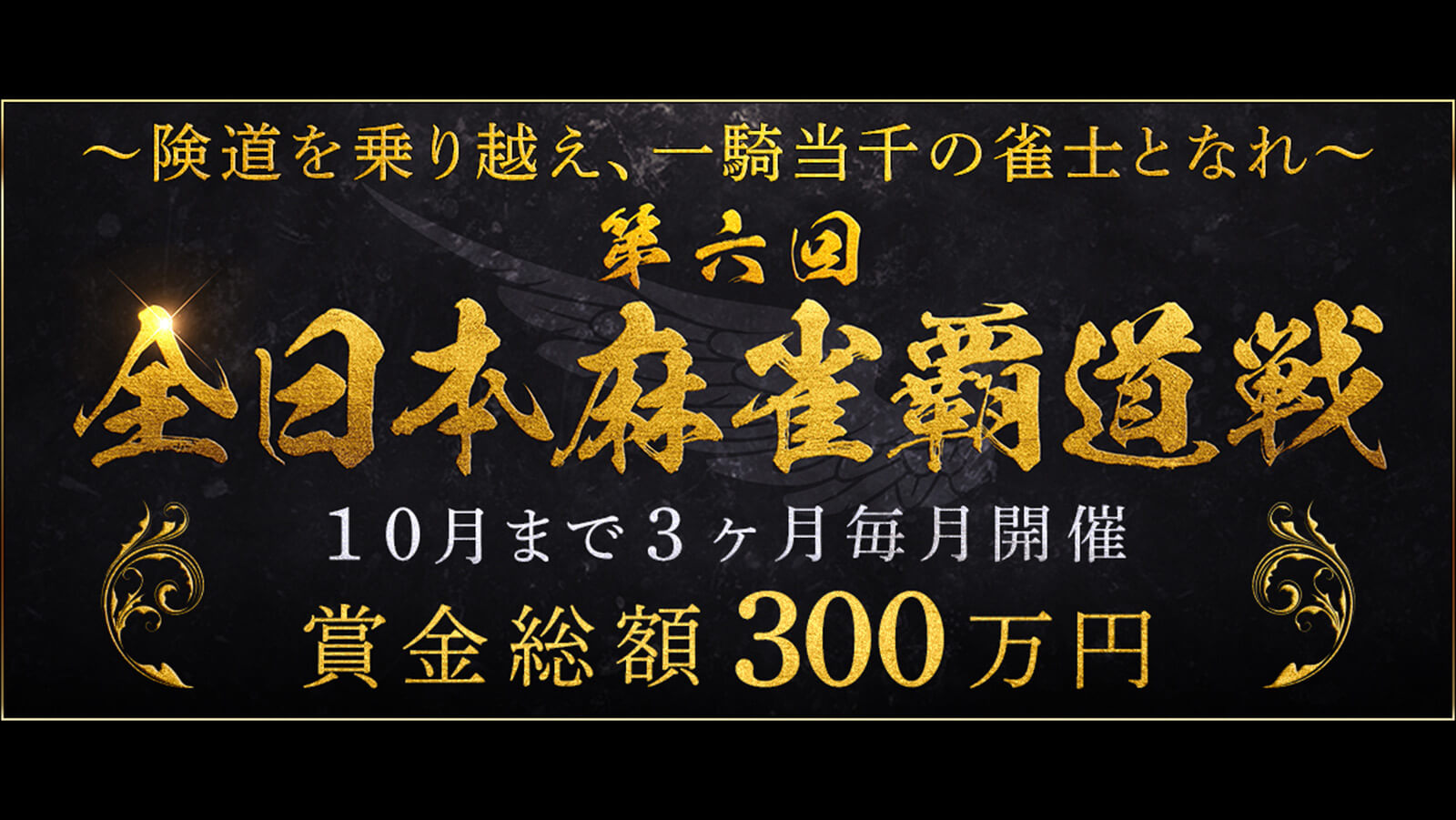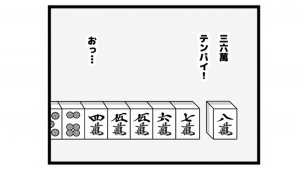~「麻雀界 第8号」より転載~
トラブルの種類は様々あって、その対応も店によっても違うこともしばしば。
今回は大貝プロが、起こりやすいトラブルを分類。全部覚えて大貝プロの裁定とともにグッドマナーに努めよう!
ここ数回マナーについて書いてきましたが、今回はトラブルに関するお話です。過去に遭遇したトラブルの内、『これはどうなのかな』と思った裁定について記してみます。
正しいマナーを励行することによって、未然に防げるトラブルがあることにも注目していただけたらありがたいですね。
配牌時での北家の少牌
今流行りの自動配牌卓ではなく、サイの目に合わせて配牌を取る卓においての話です。
以前「すでに南家が打牌しているから」という理由で、アガリ放棄と裁定されているシーンを見ました。これが私には腑に落ちなかったのです。トラブルの裁定をする時、特にペナルティを下す時は、本人の落ち度がどれくらいあるかに着目すべきでしょう。
トラブルの一因を担ったのが明白であっても、それが必ずしもその人だけの責任でないと認められるならば、無罰の裁定になることもありえるわけです。
ではこのケースはどうなのか。
まず「親は全員が配牌を取り終えてから第1打を切らねばならない」という正しいマナー(あるいはルール)を遵守していればこんな事態は起こらないはずであり、ゆえに親にも責任の大半があると私は思います。
また第1ツモの際に異変に気づいてしかるべき南家も、正しいゲームの進行に無関心であった点で無罪とは言いかねますね。
したがって北家のアガリ放棄という裁定はどう考えても重すぎるものであり、「ツモ山から北家に1枚補充させる」か、あるいは「その局をノーゲーム扱いにする」というのが妥当でしょう。
お節介にも隣の卓から主張した私のこの意見、その時は悲しいことに採用されませんでしたけど(笑)。
むろん「数巡が経過した時点で初めて少牌に気がついた」などという場合は実際に配牌の段階で起きた事態かどうかを確認する術がないわけですから、この限りではありません。
発声を伴わない誤ツモ
盲牌を間違った等の理由で、ツモアガリのごとく牌を手元にひき寄せるケースです。一番直近は新宿でのことでした。
卓のフレームにツモ牌をひき寄せた彼、潔く「すみません、盲牌を間違えました」と言ったのですが、スタッフさんの裁定は本人に誤ツモの意識があるかどうかは二の次で、「発声してないんですよね?ならノーペナルティですよ」という答え。
これには正直首を捻らざるをえません。普段は何も言わず裁定に従う私ですが、この時ばかりは思わず口を挟んでしまいました。
「その裁定だと発声しない人の方がトクすることになりますよね?」と。
『なんだ、口を挟んでばかりじゃないか』と思われるかもしれませんが、まあそういう性格なのです。
「いやまあそうかもしれませんが、うちは発声が基準なので…」とスタッフさん。私は大人なので、それ以上ゴネてたりはしません(笑)。
しかし『動作の前にまず発声』の基本原則をちゃんと守ってる人の方が損するルールなんてありえませんよね。『ポンとチーは発声優先』という最近の傾向がまさにそうですが、裁定のしやすさだけを重視してルールを策定しようとするとおかしなことになりかねません。
本人が自ら「誤ツモです」と言っているのにノーペナとは不思議な話です。
私が昔店長をしていた店では「他家3人がツモアガリの動作だったとみなした場合は誤ツモ扱い」としていましたが、誤ツモの本人も含めてこれが一番納得いく裁定であるように思います。
いずれにしろ、『まず発声』の原則がもっと徹底されるといいですね。
点数授受後の誤申告発覚
麻雀には一事不再理という原則があり、一度点棒のやりとりが終わって次局に移った場合は修正不能ということになっています。
ところが先日私の勤務先で起こったのは、ツモられた他家が「3000・6000ですね」とパッと見で言ってしまい、アガった本人を含めた全員がそれにつられてしまったケース。
次局に入ってから実際は倍満まであったことに気づいた和了者がそれを指摘し、裁定に困ったそうです。幸か不幸か、私は不在でしたが(笑)。
この場合は頑固に一事不再理を打ち出してよいものかどうか、確かに微妙です。責任の所在がアガった人だけに限られませんからね。
代わりに点数申告をした方はもちろんよかれと思ってのことに違いないのですが結果的にトラブルの種を蒔いてしまい、他の二人も自分の払い点が合っているかどうか確認するのを怠ったことになります。そして言うまでもなく、アガった人には自分で申告する義務があったわけです。
これらを踏まえて私の同僚は本来の点数に戻すようお願いしたらしいのですが、私がその場にいてもおそらく同じ裁定をしたことでしょう。
以前書いたことの再掲ですが、麻雀においてプレイヤーは同時に審判でもあります。
誰かのアガリが出た場合、
①正しいアガリ形であるか
②フリテンになっていないか
③アガリ点の申告は正しいか
これらのことを全員が確認する義務があるわけです。加えて言えば、点棒の授受が正しく行われたかどうかまでしっかりと確認するべきなのですが。
しかるに最近のフリー雀荘の傾向として、とにかく先に進みたがる打ち手が多すぎるように思います。
『他人のアガリ手の確認など面倒くさいし点棒は言われたまま払えばいい、なにしろ一刻も早く次局の配牌が見たい』と思ってるのかどうか知りませんが、点棒の授受が始まらないうちから捨て牌を流すボタンを押したがる打ち手をよく見るのですね。
自分がアガった時でさえ、確認させる間も与えずに牌を落とそうとします。私がやっぱり一言口を出すシーンです(笑)。
みんながアガリ手の確認をし、行き交う点棒を箱に収め始めるまで待ってからボタンを押したとしても、余分にかかる時間は10秒程度のものでしょう。
点棒をしまうのに気をとられて第1ツモをしないまま打牌してしまったとか、捨て牌を流した瞬間に「今の手、フリテンだった気が…」という声が上がったりするようなトラブルを避けられるならば、その10秒はけして無駄ではないと思うのです。
心ない上司に「とにかくどんどん局を進めろ」と指示されている気の毒な雀荘スタッフでもない限り、誰もが納得いくゲームの進行に必要な時間を惜しまないようにしましょう。
本来のツモ牌でない牌でのツモアガリ
ツモる場所を間違え、それがたまたまアガリ牌だったというケースです。もちろんそれをツモ切って他家にロンされた場合も含みます。お店によってそれぞれハウスルールがあることは承知していますが、これが最も裁定が分かれるトラブルではないでしょうか。正規の牌をツモり直させてノーペナルティ、もしくはアガリ放棄、場合によってはチョンボさえ。
私の見解は、意外に思われるかもしれませんがアガリ成立です。
先に申したようにプレイヤーはみな審判です。件の打ち手が誤った牌に手をかけた瞬間に異議を唱えなければなりません。卓内でメールしている場合ではないわけですね(笑)。
三人全員がその義務を怠った以上、アガリを認められて点棒を払うのもやむをえないと思う次第です。
特に全ての牌山が短く、ツモり間違いが起こりやすい自動配牌卓においてはありがちなトラブルです。少なくなった牌山を寄せる際に上家の山から離しすぎてしまうと末尾の1牌が視野から外れやすいことと合わせ、注意しておきたい項目ですね。
それでは今回はこのへんで。
皆さんの麻雀ライフがより豊かなものになりますように。
著者:大貝博美
プロフィール:昭和35年、東京都生まれ。101競技連盟所属。第22・30期王座。ファミレス店店長を経験後、競技麻雀に惚れこみ、麻雀プロの世界に足を踏み入れる。
出展:本ページは(株)日本アミューズメントサービス様からの転載許可に基づいて掲載しております
本記事に関するご紹介

6ヶ月定期購読:3000円(税込・送料込)