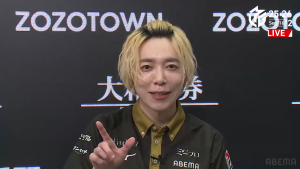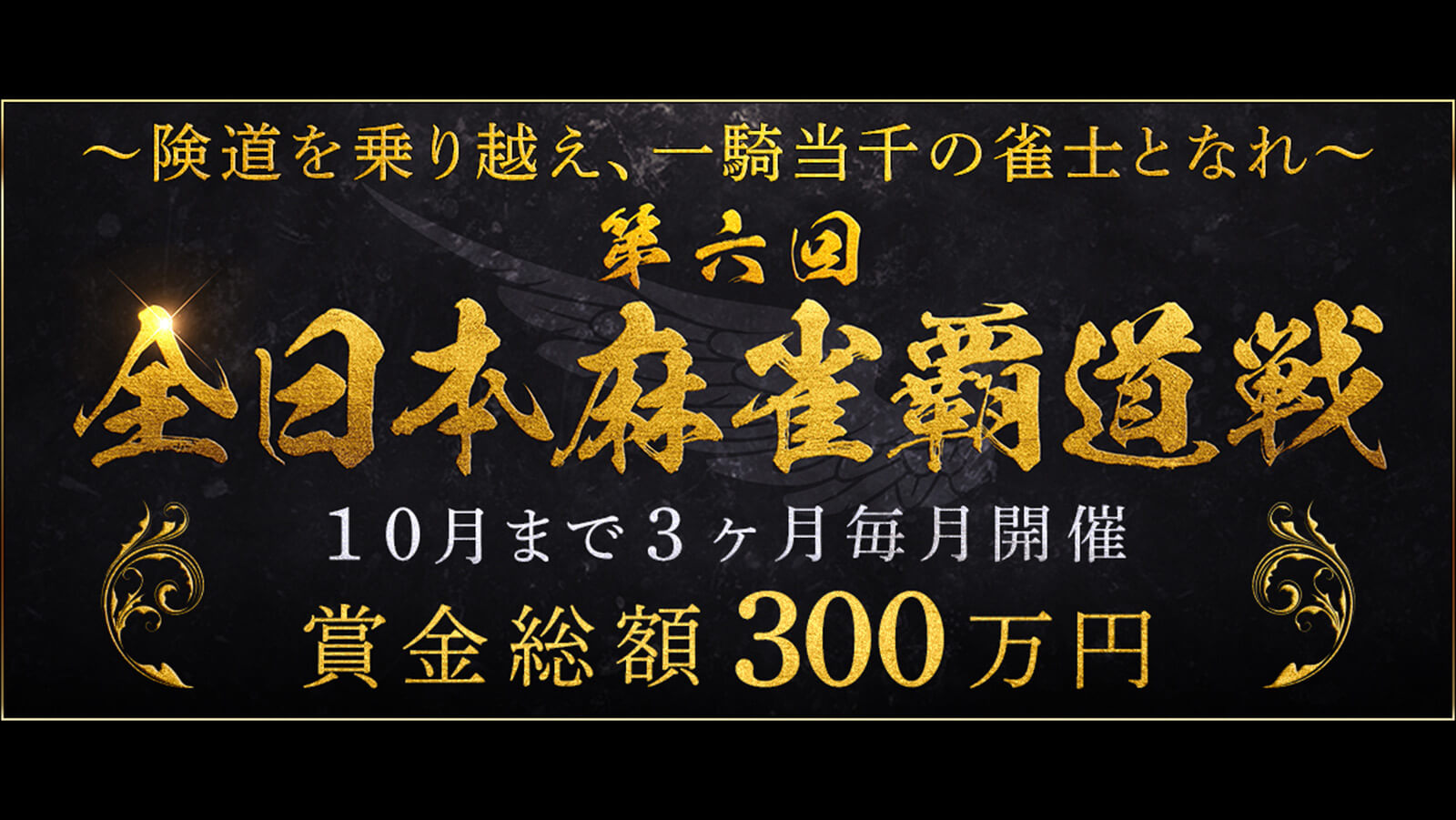四限目 講座5
基本は鳴きの受け入れより、高打点が狙いやすいメンゼンの受け入れ優先ですが、メンゼンで進めるメリットが小さい局面であれば鳴きの受け入れを重視する場合があります。手役狙いというと打点を重視するイメージですが、打点が不要な局面だからこそ鳴いてもアガれるように手役を狙うこともあるというのが面白いところです。
他家にアガリ牌を特に止められやすいのでなければ、鳴いてテンパイであればカンチャン待ちであっても、リャンメンリーチと同程度にはアガれます。鳴き手のテンパイは手変わりがあるか、手変わりが無いけど待ちが端寄りなので比較的アガリやすいというのもあるので、打点が不要であれば役無しリャンメンリーチよりはカンチャンでも鳴いてテンパイできる受け入れを優先と言えます。
ただし、鳴ける形といっても、実際に他家から鳴ける牌が切られるとは限りません。上家にとって必要な牌であるか、絞られた場合は鳴けないので、上家からのチーテンが利く手であっても、1巡あたりのテンパイ率は2倍にまではならないことが多いです。
チーできる牌を2倍、ポンできる牌を4倍として受け入れを数えてもテンパイしやすさに大差ない場合はメンゼンの受け入れが多い方を基本的に優先します。(点数状況的に上家からのアシストが期待できる場合は別ですが、アシストできるかは上家の打ち筋によるところが大きいです。これについては、三限目講座18で申しましたように、人読みが当たった時と外れた時のリスクリターンを踏まえたうえで判断しましょう。)
図Aについて、![]()
![]() ポンはドラ待ちが残るので鳴き手とはいえアガリづらいですが、
ポンはドラ待ちが残るので鳴き手とはいえアガリづらいですが、![]()
![]() をチーして
をチーして![]()
![]() 待ちであれば他家から切られる可能性も高いので、上家からの
待ちであれば他家から切られる可能性も高いので、上家からの![]()
![]() チーがまずまず期待できるなら打
チーがまずまず期待できるなら打![]() の方がアガリやすいと言えそうです(上家がアガリを目指しているなら序盤からは中張牌は鳴きにくいので打
の方がアガリやすいと言えそうです(上家がアガリを目指しているなら序盤からは中張牌は鳴きにくいので打![]() )。
)。
打![]() として
として![]() が出た場合も
が出た場合も![]()
![]() で鳴いて打
で鳴いて打![]() とします。
とします。![]()
![]()
![]() から面子を崩して
から面子を崩して![]()
![]() でチーは不自然なので
でチーは不自然なので![]()
![]()
![]()
![]() の形が読まれるかもしれませんが、
の形が読まれるかもしれませんが、![]()
![]() が他家から出ないとしても鳴きがきく完全1シャンテンなら悪くないのでスルーするほどではないでしょう。
が他家から出ないとしても鳴きがきく完全1シャンテンなら悪くないのでスルーするほどではないでしょう。
図B、Cは鳴いてカンチャンテンパイなら役無し36リャンメンリーチよりはアガリやすい。しかし2枚のトイツは他家から鳴けるとは限らないのでリャンメンを崩すのはやりすぎということでどちらもカンチャン固定がアガリやすいと言えそうです。
図Dはメンゼンなら良形テンパイ確定で、図Aのようにチーした時にリャンメンが残りませんが、2シャンテンとなるとテンパイまでに鳴ける牌が出ることが1シャンテンの場合よりも多いので、今回も鳴ける受け入れ優先でよいとみます。ドラ![]() ならドラやドラ表示牌でも優先的に切る(上家がこちらにアシストしてくる場合や、ラス目が国士狙いの場合など)と読める他家がいるのでないなら打
ならドラやドラ表示牌でも優先的に切る(上家がこちらにアシストしてくる場合や、ラス目が国士狙いの場合など)と読める他家がいるのでないなら打![]() とします。
とします。
本記事に関するご紹介
今回は中級者を完全に脱出するために、前著の内容をグレードアップ。ライバルの一歩先をいく手順や鳴きのテクニックから、立体牌図を使った押し引き判断、トップをもぎ取るためのオーラスの攻め方まで、あらゆる局面で使える実践打法を網羅。本当の強者になりたい人、必読の書!