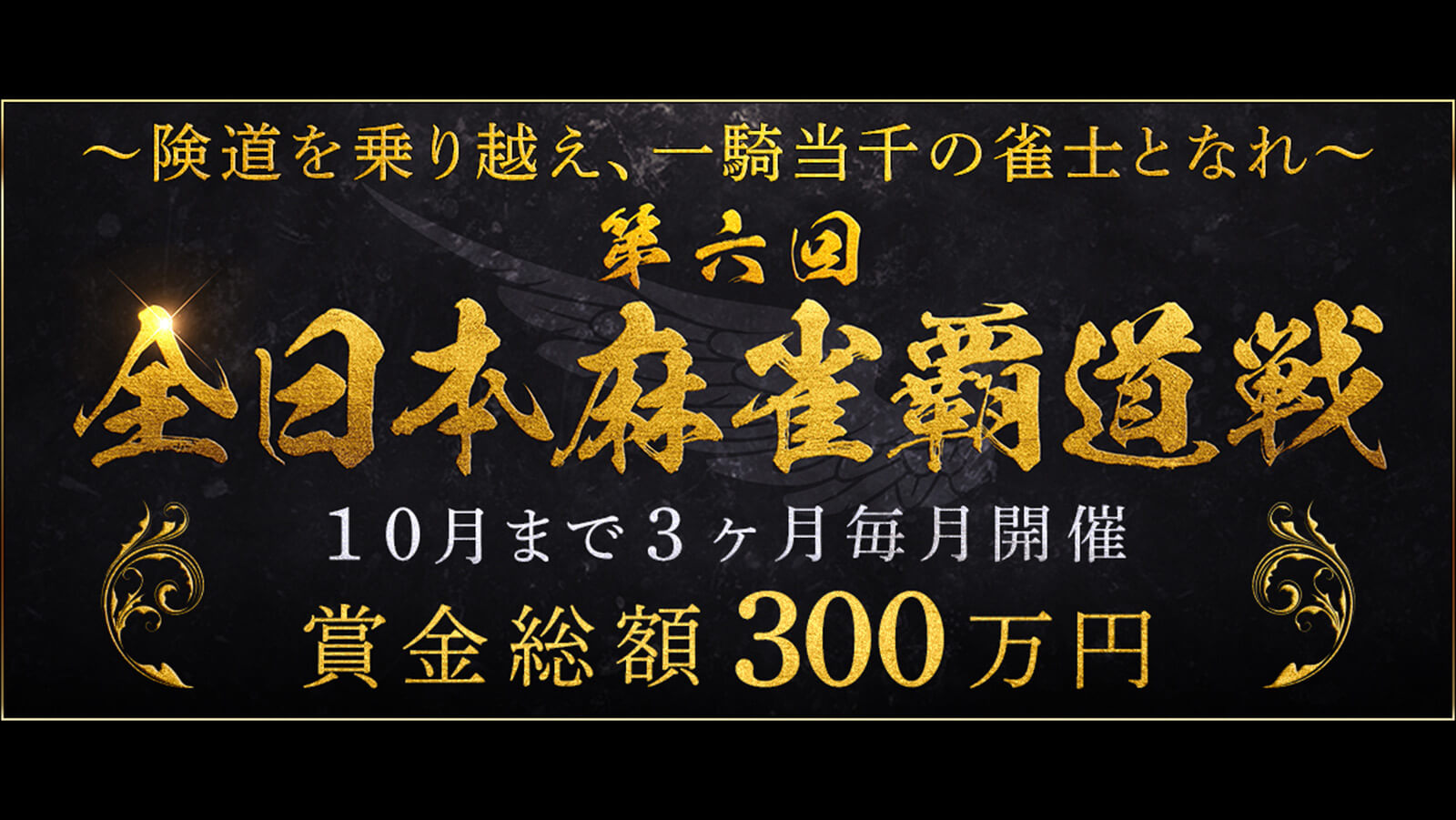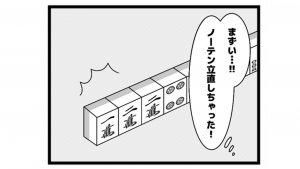- 『ネマタの戦術本レビュー』は、麻雀戦術サイト「現代麻雀技術論」の著者・ネマタさんによる戦術本レビューです。
- ご意見・ご感想がありましたら、お問い合わせフォームから送信してください。
- 第1回から読みたい方は、目次からご覧ください!
当レビューは書籍の内容に関するネマタ氏が当書の回答に異論があるもの、追記事項があるもの、または更に掘り下げたい部分等を取り上げます。姿牌、局面については書籍を購入してご確認下さい。
▼書籍版
▼Kindle版
第2章 スタンダードな押し引き
6.点数状況
①親落ち断ラスの猛攻
親落ち断ラスで具体的にどのように打てばよいかについてまとめられている戦術記事を見ません。体系化するのが困難であることに加え、仮に最善を尽くしたところで報われる(ラス回避)可能性が低いので重要度が高くないこともその理由として挙げられるでしょうか。
今回の局面だけ見れば、ダンラスだから追いかけリーチもやむなしと判断する人も多いと思いますが、それまでの道中で手が進む牌を鳴かず、リーチに![]() 2枚切れから両無スジ
2枚切れから両無スジ![]() を迷わず押せる人は果たしてどの程度いるでしょうか。「この点数状況からこの手をアガった時に、最終的なpt期待値はいかほどになるのか。」このあたりは人間の感覚で何とかなるものでもなく、AIの計算がものを言う領域。最も勉強し甲斐のある分野と言えるかもしれません。
を迷わず押せる人は果たしてどの程度いるでしょうか。「この点数状況からこの手をアガった時に、最終的なpt期待値はいかほどになるのか。」このあたりは人間の感覚で何とかなるものでもなく、AIの計算がものを言う領域。最も勉強し甲斐のある分野と言えるかもしれません。
②ラス前の後手判断
先制リーチなら多少リードしている程度ならラス前トップでも基本はリーチ。2着目と僅差で放銃で着順落ちしやすいケースほど、リーチによる加点で2着目以降と点差を付けるメリットも大きくなるうえに、そもそもリーチしたところで放銃率はそこまで上がらないためです。
しかし後手となれば、「一定の危険度以上の牌を引けば降り」を選ぶことで放銃率を大きく軽減することができます。フラットな点数状況では、「よほどの危険牌を引かなければ降り有利にならず、よほどの危険牌を引く前に自分がアガるか他家がツモアガリすることが大半」なので降りを公算に入れない手であっても、打点上昇の恩恵が小さいとみてダマにするケースが生まれます。
今回はダマ2000点を対門からアガっても、オーラス2着目の上家とは5100点差。一人ノーテンでもトップを維持することができるうえに、自分が東家なので必ず一局で終了します。高めなら更に盤石。リーチで更に加点したとしても、ここでの放銃率以上にまくられ率を下げることにはならないとみてダマが有力そうです。
③対ライバル
ここでのライバルとは、放銃した場合と、降りて被ツモや横移動した場合とで最終的なpt期待値があまり変わらない他家のこと。リーチ者がラス目だったとしても、このケースは結構押し寄りになるということが実戦譜からも再確認できます。
リーチの現物待ちでドラも多く見えているので、点差が大きく離れた南家西家からの出アガリが期待しやすいのもポイント。今回くらいのケースなら直感的にも押すところなので、もう少し降り寄りの条件が揃った時にAIがどう判断するのかが気になります。
世界最強麻雀AI Suphxの衝撃

世界最強の麻雀AIを人間のトッププレイヤーが本格解説!
2019年6月、麻雀AIで初めて天鳳十段に到達し話題をさらった「Suphx」(スーパーフェニックス)。
天下のMicrosoft社が麻雀という不完全情報ゲームに殴り込みをかけてきたのです。「Suphx」の強さはもはや人間のトップレベルに達しており、他のボードゲームがそうであるように、麻雀も「AIから学ぶ」時代に突入しつつあります。
本書はその端緒となるもので、最強のAIである「Suphx」を人間界のトップといえる天鳳位を獲得したお知らせ氏が徹底的に解説するのものです。
お知らせ氏の筆致は処女作である『鬼打ち天鳳位の麻雀メカニズム』で証明されたように緻密にして正確無比。「Suphx」の打牌を咀嚼し、人間の知として昇華する上でこれ以上の適任はいないでしょう。
ぜひ本書で「Suphx」の強さの秘密と、麻雀というゲームの深淵を味わってください。
●目次
第1章 強くなること
第2章 スタンダードな押し引き
第3章 中盤のスリム化
第4章 序盤の方針
●著者プロフィール
1989年9月18日生まれ。
神奈川県横浜市出身。東京大学工学部卒。
第14代四麻天鳳位。
著書 「鬼打ち天鳳位の麻雀メカニズム」(マイナビ出版)
購入はこちら
▼書籍版
▼Kindle版