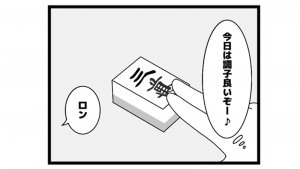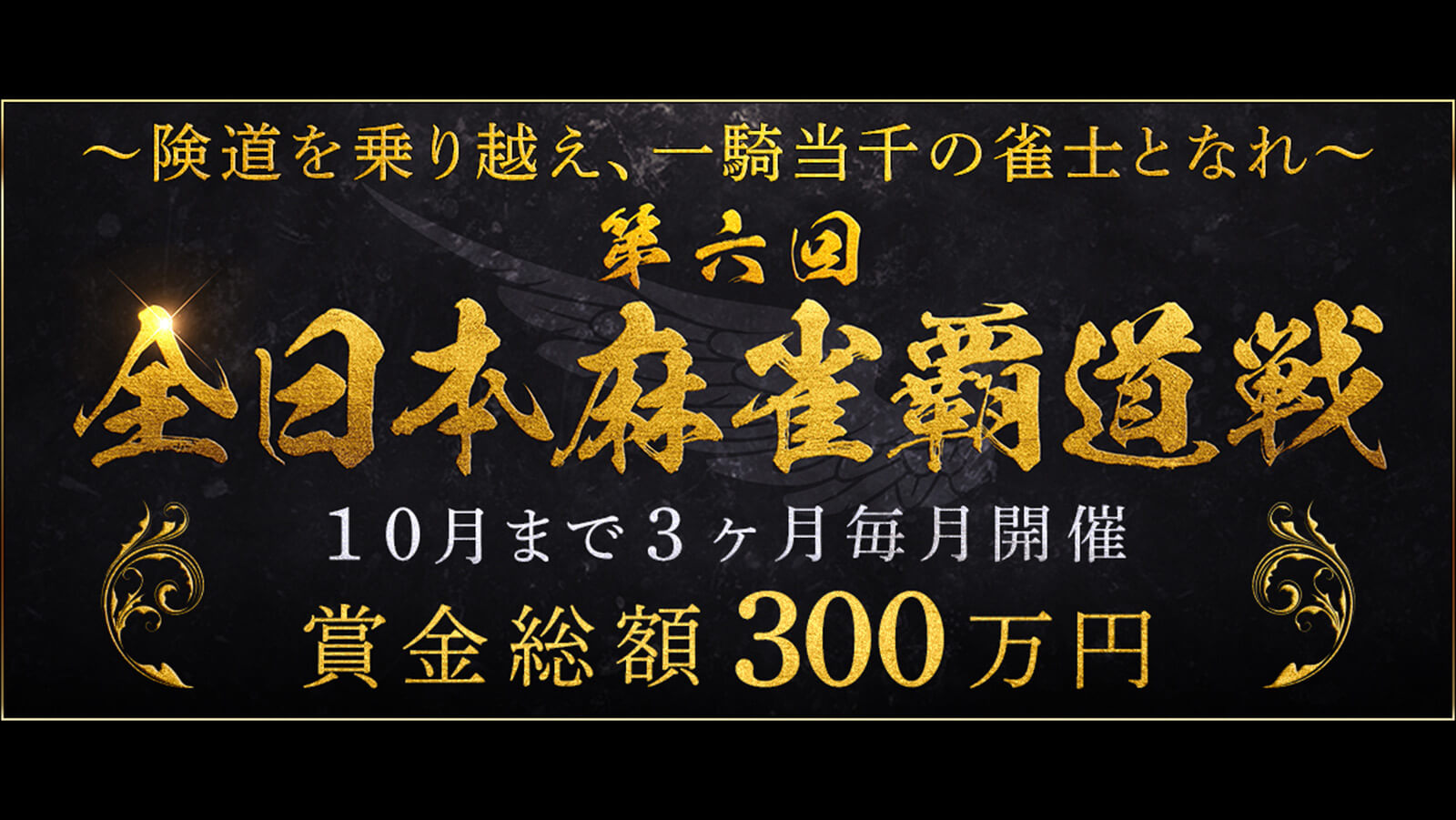- 『ネマタの戦術本レビュー』は、麻雀戦術サイト「現代麻雀技術論」の著者・ネマタさんによる戦術本レビューです。
- ご意見・ご感想がありましたら、お問い合わせフォームから送信してください。
- 第1回から読みたい方は、目次からご覧ください!
テーマ 17
受けを狭めてまで迷彩を施すという選択が有力になることはあまりありません。特に手牌Aのような場合は、平和や三色がつかなくてもリーチツモで満貫に届く(ツモの1翻の価値が高い)、リャンメン待ちが残るなら他家にアガリ牌を止められてもツモりやすく、迷彩を施したところで無筋なのでさほど出アガリやすくならない…というように、河を作る効果が薄いと言えます。
手牌Bは先切りによって高め三色で出アガリしやすくなり、三色にならない手なので、押し返しやすいように攻撃的安牌を抱えるという狙いも含めれば![]() 先切りも有力そうです。
先切りも有力そうです。
もちろん、手組に関して他に差が無ければ出アガリしやすいように河作りを意識するに越したことはありません。手牌C、Dがその一例ですが、メンゼン手か鳴き手かで打牌が変わるというのは意識していなかったので参考になりました。
テーマ 18
ホンイツは鳴いて作ることが多い(鳴き手はツモの1翻がつかない)、他家から鳴ける牌が出るかどうかでアガリ率に差が出やすい、高打点になりやすいので特にアガリ率を高めたい…というように、河を作る効果自体は比較的高いと言えます。手牌Aや手牌Cのように、ターツが揃っていれば使わない一色牌を先に切って河を作るようにしましょう。
しかし使える牌が限られているので、迷彩を施せるケースはあまり多くありません。実戦ではターツを揃えるためにメンツになりにくい端牌や孤立字牌を抱えてまで染めることになるので、「見え見え」の染め手になりやすいものです。
しかしそのような場合は、「見え見え」になってもさほど問題ではありません。こちらがテンパイ、相手がテンパイに遠いノーテンなら、テンパイとバレずに対応されない方が有利ですが、こちらがテンパイに遠いノーテンなら、むしろ対応してくることで他家のアガリ率を落とせるようならむしろメリットになります。
難しいのは手牌Bのように、ターツが足りてないとはいえ、多少受けを狭めてもターツを揃えやすい場合。本書ではこの時点では迷彩を施さないとありますが、個人的には最序盤なら![]() を切ります。後からでもホンイツはぼかせるとありますが、最序盤からいきなり
を切ります。後からでもホンイツはぼかせるとありますが、最序盤からいきなり![]() が切られたケースと字牌から切られたケースとでは、ホンイツと読まれないとしても仕掛けへの対応で結構差がつくと予想されること。巡目が早ければ多少受け入れを狭めてもアガリ率が下がりにくいことがその理由です。
が切られたケースと字牌から切られたケースとでは、ホンイツと読まれないとしても仕掛けへの対応で結構差がつくと予想されること。巡目が早ければ多少受け入れを狭めてもアガリ率が下がりにくいことがその理由です。
テーマ 19
テーマ17で、リャンメン待ちが残りやすい、メンゼンツモの価値が高い手は基本迷彩不要と書きました。逆に言えば、悪形待ちが残りやすい、安め高めがあって高めなら出アガリでも高打点になる場合であれば、受け入れや変化で多少ロスがある程度なら河を作ることも有力になりやすいです。うまく使い分けられるようにしたいですね。
麻雀 だから君は負けるんです

勝ち組は「麻雀で勝つために必要な知識」をたくさん持っているから勝ち、負け組はその知識の量が少ないから負けるのです。この本では麻雀で勝つために必要で、なおかつ絶対に持っていなければいけない特に大事な知識や考え方を紹介しています。
Kindle Unlimited
購入はこちら