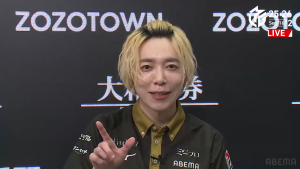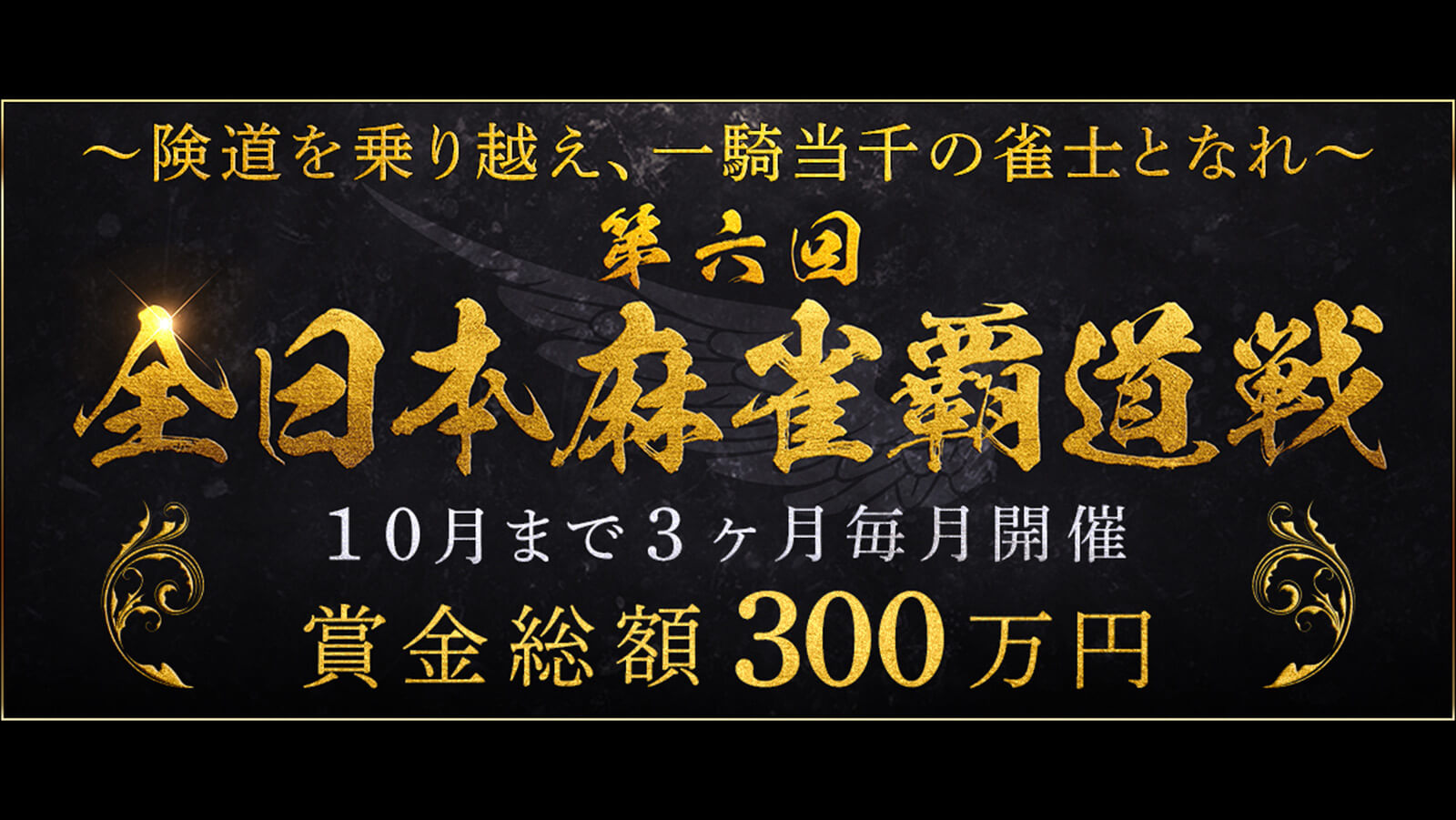第五章 読み
(8)「即リーチが原則」というのは、現代の麻雀戦術の基本が身に付いていらっしゃる方であれば常識だと思いますが、誰もが現代的な麻雀戦術を学んでいるわけではないので、打ち手の母集団によってはツモ切りリーチが頻発することもあります。
例えばMJにおける私のツモ切りリーチは2%未満ですが、全国平均は10%を超えていて、1巡回しが癖になっていると思われる程ツモ切りリーチを連発する打ち手と同卓したこともありました。
このようにツモ切りリーチの頻度は人によってまちまちで、意図についても様々ではありますが、手牌の出現頻度的にも、点数や待ちに不満があって手変わりを考慮していたケースが最も多いというのは確かです。待ちが悪いことを他家に読まれてしまうのは損なので、その点からも即リーチすべきということが言えます。
逆に言えば、損なツモ切りリーチは極力打たないことを徹底している打ち手がツモ切りリーチしてきた場合は、それこそ手牌Eのように、ダマのままあがっても十分高打点のケースが多いので特に警戒した方がよさそうです。打ち手によって大きく傾向が変わるところなので、可能であれば他家の打ち筋を調べることも必要なことかもしれません。
(9)どちらを切っても手牌の価値も、手が進む牌のツモりやすさも大差ない場合は、捨て牌情報量が少ない、すなわち「河が強い」方が有利になります。ヤオチュウ牌しか切っていない段階でリーチが入れば手牌をほとんど読みようがないように、内寄りの牌が少ないほど河が強くなると言えます。
第六章で迷彩について取り上げられていますが、迷彩になる場合を除いては、字牌や外側の数牌から切っていく、いわゆる「手なり」で打つ方が、結果的に河も強くなりアガリやすくなることが言えます。ですから、今回の項はあまり意識してなかった方も多いかと思われますが、実は自然とできることなのでそれほど意識しなくても大丈夫です。
(10)(9)に引き続き河の強さの話。迷彩になる場合を除いては、手出しよりはツモ切りの方が河が強くなることになります。迷ってしまうと待ち選択ができるような手牌であることが読まれやすくなってしまうので、選択する必要が出る前にあらかじめ考えておいて、その時になったら瞬時に選べるようにしておくようにしましょう。選択の段階以前では時間をかけて考えてもよいので、素早く判断する自信が無い方でも実行しやすいと思います。
本記事に関するご紹介

ツキ、流れ、勢いといったあいまいな表現を嫌ってきた著者の明晰な頭脳で、麻雀を論理的に限界まで語りつくされてます。