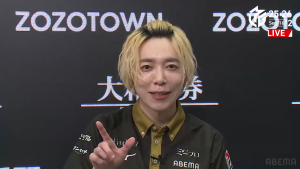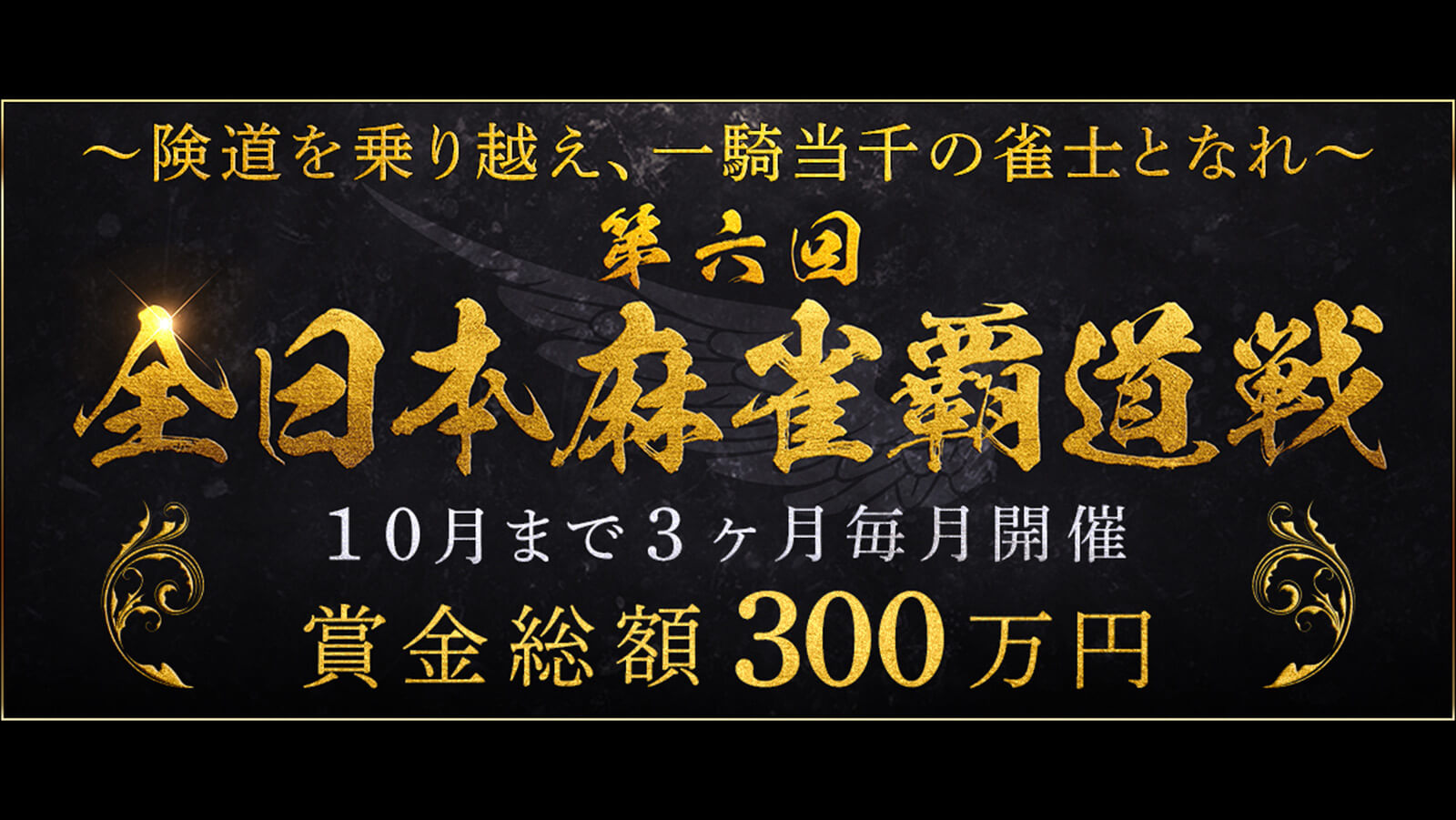第1章 押し引き
麻雀本レビュー第57回
21 打![]()
安牌が無いので仕方なく押しという見解が多いようですが、ラス目とはいえ着順争いをしている相手のリーチで、こちらもあがれば着順が上がるリャンメンテンパイであれば、天鳳ルールで安牌があったとしてもある程度は押す手であるとみます。
ただし本書でも指摘されているように、降り有利になるような状況の変化があっても、テンパイだからといってずっと押し続けるのは禁物ですし、「降り有利にならないギリギリのところまで押す」というのは難しいもの。ですから、気持ち早めに降りた方が大きなミスが少なくなり結果的に勝ちやすいということは言えるかもしれません。
22 打![]() リーチ
リーチ
トップと僅差ならメンゼンツモや裏ドラによる打点の上乗せの効果はむしろ大きく、先制リャンメンなら他家に追いつかれて放銃する可能性も低いので、「![]() をポンして
をポンして![]()
![]() 待ちテンパイ」との比較であってもリーチがそれほど劣るとは考えにくい。よって
待ちテンパイ」との比較であってもリーチがそれほど劣るとは考えにくい。よって![]() ポンの手変わりを待つくらいなら即リーチします。
ポンの手変わりを待つくらいなら即リーチします。
「役牌雀頭のリーチは避ける」という古いセオリーがあります。確かに役有りへの手変わりが多いほどダマ寄りになりますし、天鳳ルールであれば放銃のリスクも大きいのでリーチを打たない手組の価値自体は上がりますが、役有りへの手変わりを待った方がアガリ率自体も高い(例えば今回なら、ピンズが![]()
![]() なら打
なら打![]() とする)というのでなければ、判断基準を変えるほどではないとみます。
とする)というのでなければ、判断基準を変えるほどではないとみます。
23 打![]() リーチ
リーチ
仮に![]() が危険牌である場合や、待ちが悪い場合であっても、降り有利にまではならないとみて追っかけます。本書でも申し上げておりますが、安牌を切ってメンゼンテンパイの場合、次の無スジを引いても降りないなら追っかけリーチ、降りるのであればダマ、「特定の牌を引いた時だけ降り」というのは基本考えなくてよいというのを私は一つの目安としています。
が危険牌である場合や、待ちが悪い場合であっても、降り有利にまではならないとみて追っかけます。本書でも申し上げておりますが、安牌を切ってメンゼンテンパイの場合、次の無スジを引いても降りないなら追っかけリーチ、降りるのであればダマ、「特定の牌を引いた時だけ降り」というのは基本考えなくてよいというのを私は一つの目安としています。
24 打![]() リーチ
リーチ
親で良形テンパイの時点で、やはり簡単には降り有利にはなりません。押しを選ぶ問題の方がだいぶ多くなりましたが、降り有利になる要因自体は非常に多くあるので、「問題として出題されたら迷わず降りるが、実戦では降り有利になる要因を見落として押しすぎてしまう」例が結構ある、「降り有利になる要因を見落とさない人はしばしば降りすぎてしまうが、見落としが多い人に比べれば能力が高く成績もよくなる」というのが現実ではないかと思います。
25 ![]() チー打
チー打![]()
「危険牌を切って良形テンパイ」の方が、「安全牌を切って悪形テンパイ」に勝るというのが原則ですが、今回はリーチ者が7mより先にドラ6sを打っていることから![]() は面子候補の一部で
は面子候補の一部で![]()
![]()
![]() からの
からの![]() 切りが想定しやすい。
切りが想定しやすい。
また![]()
![]() は他家から出にくい一方、
は他家から出にくい一方、![]() はリーチには通る牌なので出やすい。更にはそれほどアガリのリターンが大きくないというのもあります。
はリーチには通る牌なので出やすい。更にはそれほどアガリのリターンが大きくないというのもあります。
これだけ条件が重なれば打![]() でしょうか。一つの要因だけでは判断を変えるほどではないが、複数重なる場合もあるので、単にセオリー通りに打つだけでなく、情報を見落とさない認識力が重要であることを確認させられる良問であると感じました。
でしょうか。一つの要因だけでは判断を変えるほどではないが、複数重なる場合もあるので、単にセオリー通りに打つだけでなく、情報を見落とさない認識力が重要であることを確認させられる良問であると感じました。