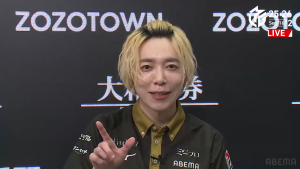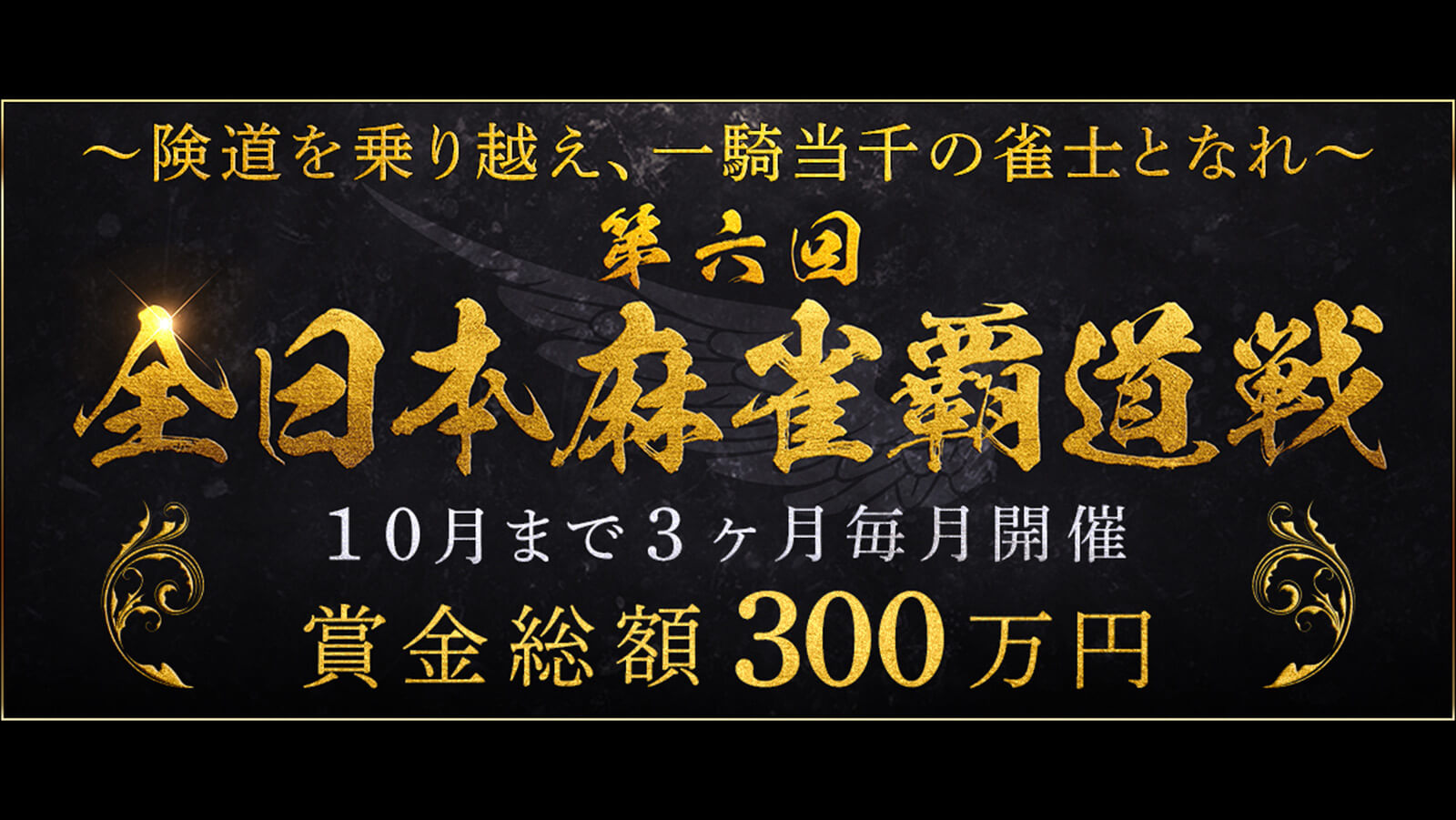第二章 麻雀はこんなゲーム
(7)一発と違い、海底については流局間際にずらすことによるデメリットが特に無いので、明確にテンパイしている他家に海底が回る場合は可能な限りずらすべきです。ずらした結果他家にツモられることが気になる方は、後述の、「同様に確からしい」「揺れない強さ」の項目を何度も読まれることをお勧めします。
リーチ者に通ることが読めるアンコで持っている牌を切って、合わせ打ちされた牌を鳴いて海底をずらすという選択は私も記事を読んで目から鱗でした。ベタオリしているのに、流局間際までリーチ者に通ると読めるアンコが手牌にあるというケースはあまり無いと思いますが、考え方自体は押さえておきたいですね。
海底牌をツモるのが誰になるかを確認する方法については、渋川難波著、『魔神の読み』に掲載されているのでこちらで引用させていただきます。
鳴きが入ってなければ海底は南家
上家から鳴くと+1か-3
対門から鳴くと+2か-2
下家から鳴くと+3か-1
カンが入ったら+3か-1
(プラスとマイナスが打消しあうように計算する)
計算の結果
0なら南家が海底
+1か-3なら西家が海底
+2か-2なら北家が海底
+3か-1なら東家か海底
(8)「同様に確からしい」ものを、「同様に確からしくない」とみなしてきた。「流れ論」に代表される従来の麻雀戦術論の誤りを一言で表せばこうなるでしょうか。「同様に確からしい」。確率を考えるうえで重要な前提条件です。
同様に、「同様に確からしくない」ものを、「同様に確からしい」とみなしてしまうのもまた誤りです。「デジタル」に対する不当なレッテル貼りの内容も一言で表せば、「デジタル」は「同様に確からしくない」ものまで、「同様に確からしい」ものとしていると言えそうです。
ただ、従来の麻雀戦術論を批判する一方、「同様に確からしくない」ものまで、「同様に確からしい」ものとみなして戦術論が展開されているような例が一部存在していたことは事実です。麻雀において数字が出てきた場合、それが何を意味しているのかについては注意してみておく必要があります。さもなければ同様の誤りを犯すことになりかねません。
問題については私も十分なデータを持ち合わせているわけではないので、分からないとしか言えませんが、どちらかを選べと言われれば![]()
![]() です。
です。![]() を切っている他家は
を切っている他家は![]() を持っている可能性が低いですが、
を持っている可能性が低いですが、![]() も持っている可能性は低い。
も持っている可能性は低い。
一応![]() は持ってないが
は持ってないが![]() を持っている例も考えられなくはないが、5s以外は字牌しか切られていないような序盤ではレアケース。一方、
を持っている例も考えられなくはないが、5s以外は字牌しか切られていないような序盤ではレアケース。一方、![]() と
と![]() の切られやすさには有意な差があり、手牌や打ち手の打ち筋によっては字牌より先に切られることも多々ある
の切られやすさには有意な差があり、手牌や打ち手の打ち筋によっては字牌より先に切られることも多々ある![]() が切られていない分
が切られていない分![]()
![]() の方がツモりやすいという判断です。
の方がツモりやすいという判断です。
本記事に関するご紹介

ツキ、流れ、勢いといったあいまいな表現を嫌ってきた著者の明晰な頭脳で、麻雀を論理的に限界まで語りつくされてます。