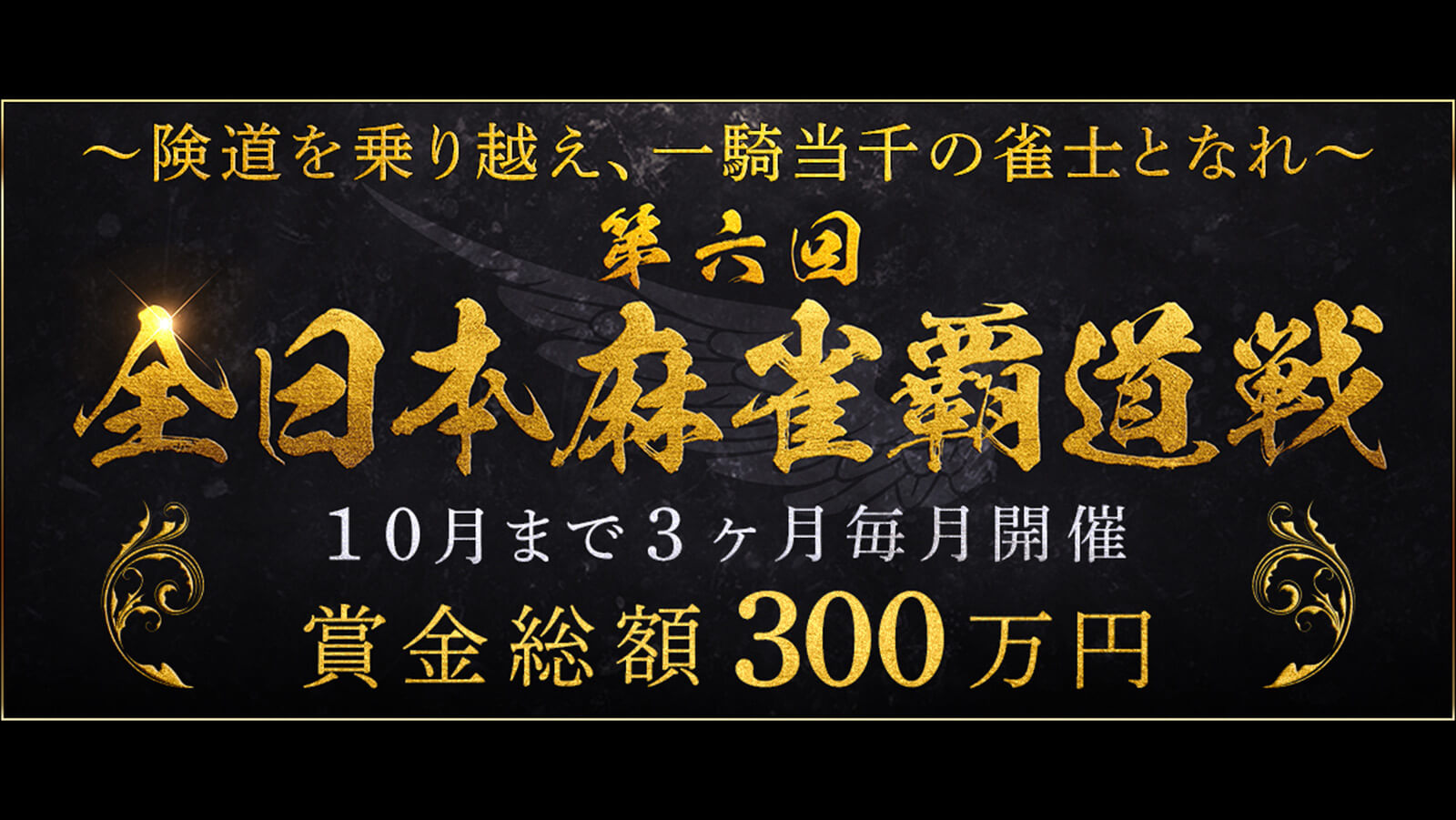第5章テーマ29
字牌の切り順が結果に影響することはあまりありませんが、局面に応じた字牌の価値を意識できるようになること自体は重要です。システム化された打牌基準についても、何故その打牌が最善と言えるのかについて理解したうえで、考えずとも選べるまで体で身に付けましょう。そうすれば実戦でいつセオリーから外れた打牌をするかに思考を集中させられるようになります。そのようになってこそ、強者に一歩近づいたと言えるのではないでしょうか。
練習問題2については題意からは外れますが、ごく稀とはいえ三元牌が次々に重なることや、メンゼンでピンズ一通ができることも有り得るので![]()
![]() 外しとしそうです。
外しとしそうです。
テーマ30
問題のような牌姿なら先制リーチが入っても押すことが多く、手変わり自体もさほど価値が高くないので、どちらかと言えば中盤以降不要に中張牌を引っ張ってしまうことの方が戦績に悪影響を与えそうです。
とはいえ、字牌を抱えないことで河が強くなり、他家に待ちを絞られにくくする効果があることも確かです。序盤のうちは受け入れを増やす牌、安牌以外に残した方がよい牌が無いかについても意識してみましょう。
練習問題2は解説に1シャンテンとありますが実際は2シャンテン。4メンツの候補が揃ったら必要牌、不要牌を意識すると言った方が正確です。
テーマ31
問題の牌姿は一目打![]() としそうでしたが、
としそうでしたが、![]() から切って
から切って
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
のようなテンパイになった場合も手変わりで大幅に打点が上がることから打![]() のテンパイ外しが有力であることを考慮すると、確かにこの時点で打
のテンパイ外しが有力であることを考慮すると、確かにこの時点で打![]() として
として![]() ツモより
ツモより![]() をみる方がよさそうです。
をみる方がよさそうです。
今回の手牌は![]()
![]()
![]() をポンするので国士を狙うことはほぼありませんが、配牌10種で5%程度しかアガれないとしても打点を考慮すれば9種で流すより有利であることが多いのではないでしょうか。流しても次局満貫以上をツモアガリできる確率は10%にも及ばないので、ラス目で3着と満貫以上差がついているなら9種でも狙うことはそれなりにありそうです。
をポンするので国士を狙うことはほぼありませんが、配牌10種で5%程度しかアガれないとしても打点を考慮すれば9種で流すより有利であることが多いのではないでしょうか。流しても次局満貫以上をツモアガリできる確率は10%にも及ばないので、ラス目で3着と満貫以上差がついているなら9種でも狙うことはそれなりにありそうです。
本記事に関するご紹介
この本には、勝ち組の人がやっていて、それでいて今までに語られていなかったあらゆる「鳴き」テクニックがつまっています。
また、著者渾身の戦術コラムがいたるところに散りばめてあり読みごたえも抜群。
これらを学ぶことで、鳴きだけでなく麻雀自体への理解も深まり、どんなルールの麻雀でも間違いなく勝率が上がります。
AMAZON販売ページ